- 市役所試験のくわしい情報が知りたい。
- 合格に向けて計画的に学習したい。
- 自分に合った教材や講座を見つけたい。
市役所試験は、他の公務員試験よりも筆記試験の負担が軽いからと油断し、後悔するケースが多いです。
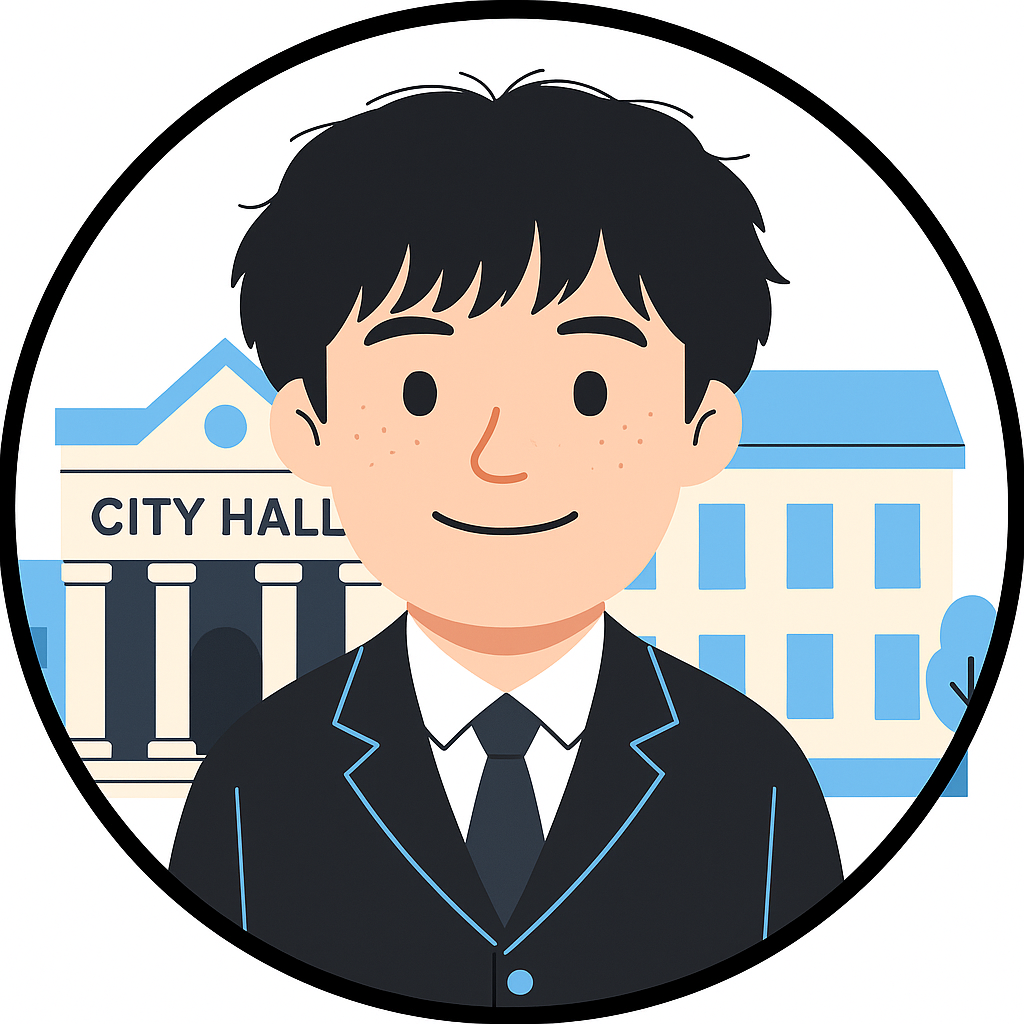
後悔しないためには、「現実的な計画」と「効率的な試験対策」が必須です。
ここでは市役所試験の合格経験を活かし、試験対策に必要な情報を解説します。
この記事を読めば、市役所試験の内容と合格者オススメの試験対策を知ることができます。
不合格になってから後悔しないように、市役所の試験対策について勉強しておきましょう!
\ 市役所に特化した公務員講座ならLEC /
市役所試験の基本情報





市役所試験ってどういうもの?
市役所試験にはさまざまな種類があり、難易度もちがいます。
最近では試験の内容も多様化しており、しっかりとした対策が必要です。
ここでは、市役所試験の種類や難易度、最新の試験傾向についてわかりやすく説明します。
試験の種類
市役所試験には「初級・中級・上級」の3つのレベルがあり、受験資格や試験科目がちがいます。
市役所では、業務の内容によって求められる知識やスキルが異なります。
そのため、試験の種類も細かく分かれており、学歴や年齢によって受けられる試験が決まっています。
| レベル | 難易度 |
|---|---|
| 初級 | 高卒程度の難易度 (例)Ⅲ類、3類、C |
| 中級 | 短大・専門学校卒程度の難易度 (例)Ⅱ類、2類、B |
| 上級 | 大卒程度の難易度 (例)Ⅰ類、1類、A |
その他にも市役所によっては、社会人経験者向けの試験があり、民間企業での経験を活かして市役所に転職することも可能です。
自分の学歴や経験に合った試験を選び、効率よく勉強することが、市役所試験合格の第一歩となります。
難易度と合格率
市役所試験の難易度は、受験する試験の種類や市役所によって差があります。
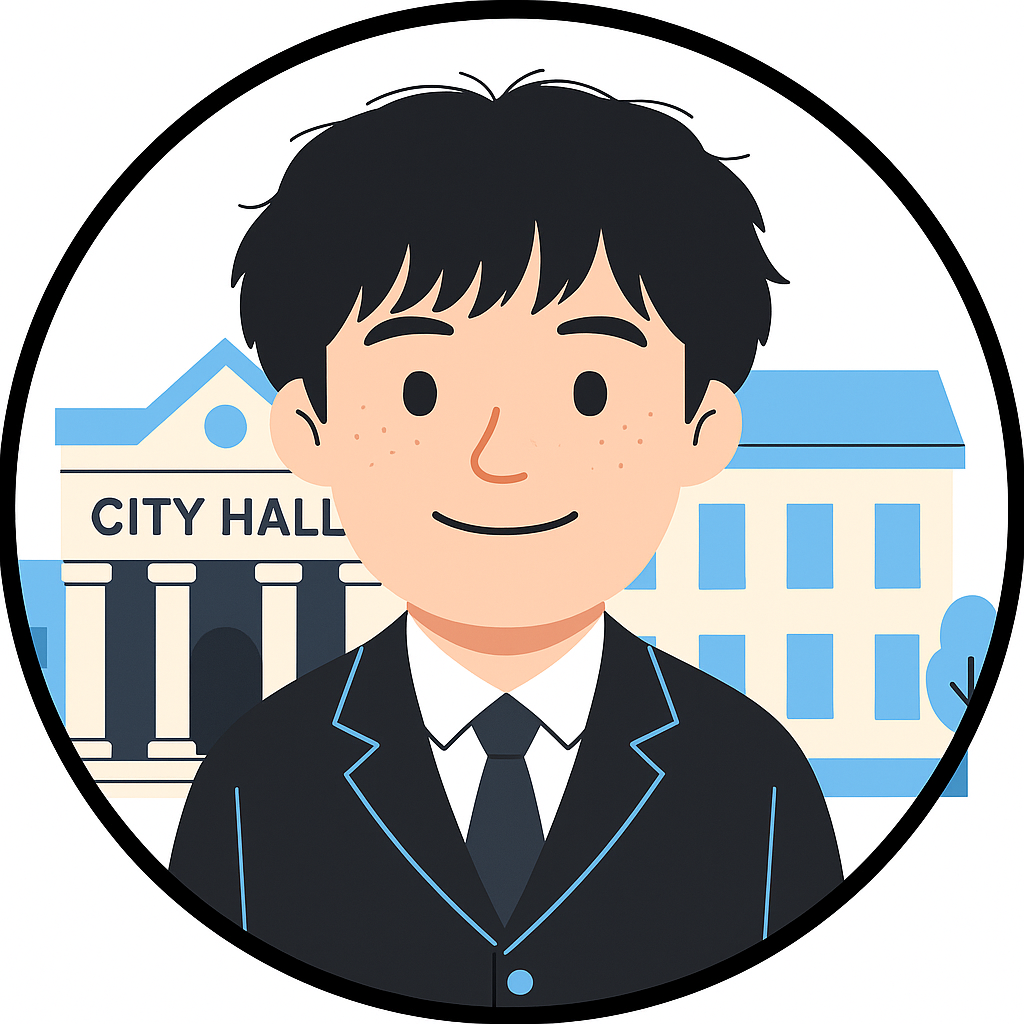
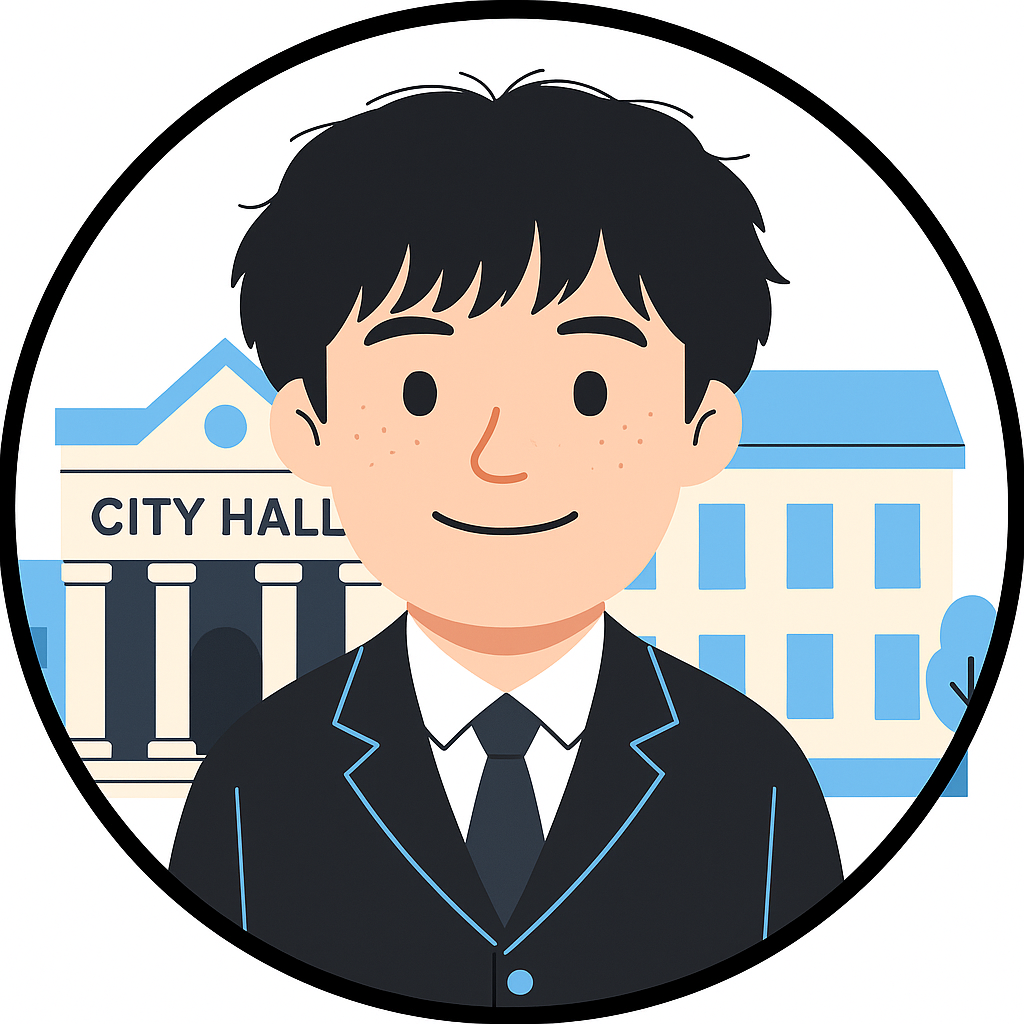
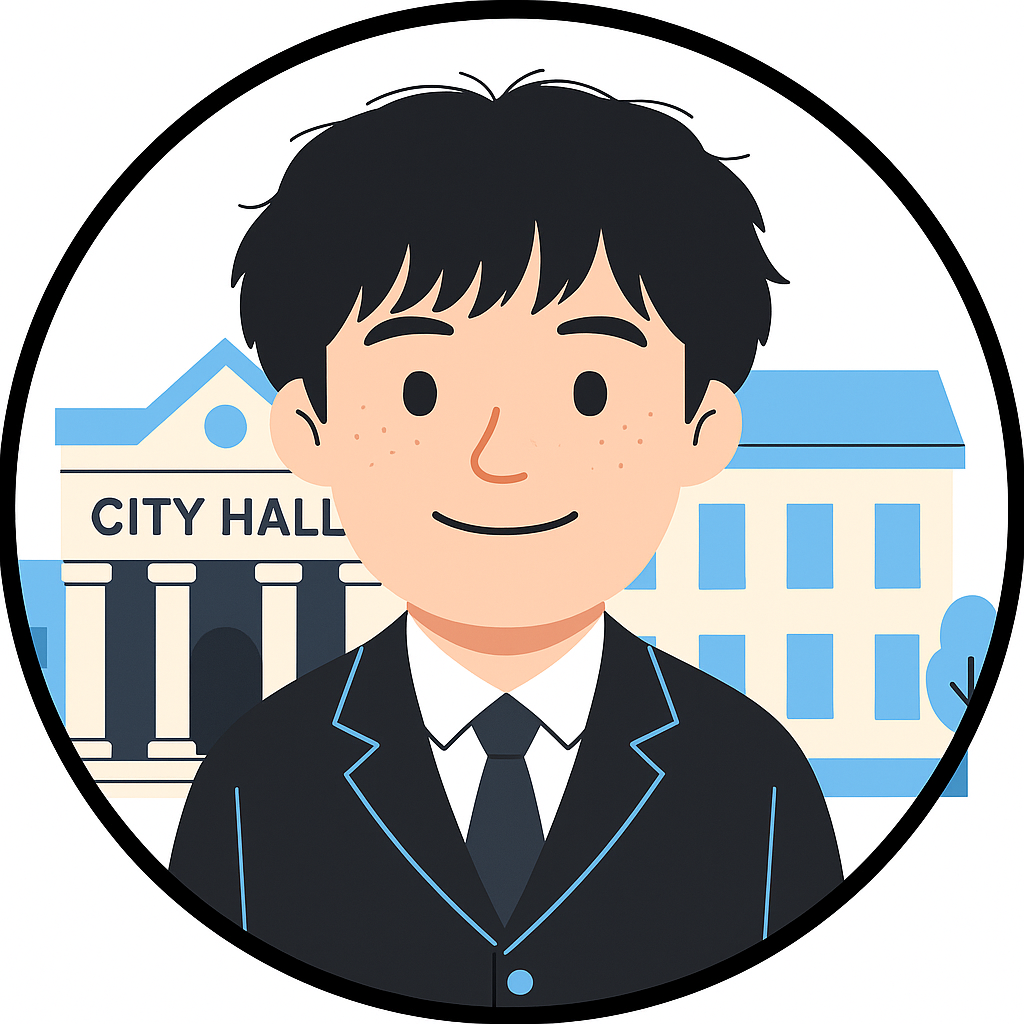
合格率は平均10~20%程度です。
試験の倍率が高いため、合格できるのは10人に1人か2人だけです。
たとえば、大都市の市役所試験は受験者数が多く、合格率が低くなることもあります。
一方で、地方の市役所試験は倍率が比較的低めですが、採用人数自体が少ないため油断はできません。
試験の多様化
従来の市役所試験には限界があると考え、試験方法を見直している市役所もあります。
- 今までの試験では、受験者が減っている。
- 予算削減のため、採用人数が減っている。
- 優秀な人材を得るために、幅広い人材を確保したい。
市役所でも人手不足が問題となっている現代。
市役所側もよい人材を確保するため、さまざまな試験を取り入れているということです。
| 試験例 | 採用側のねらい |
|---|---|
| SPI・SCOA | 民間企業への就職活動と両立がしやすくすることで、受験者数の増加を図りたい。 |
| グループワーク | グループ内での協調性やリーダーシップがある人材を採用したい。 |
| プレゼンテーション | 論理的に物事を考え、伝えられる人材を採用したい。 |
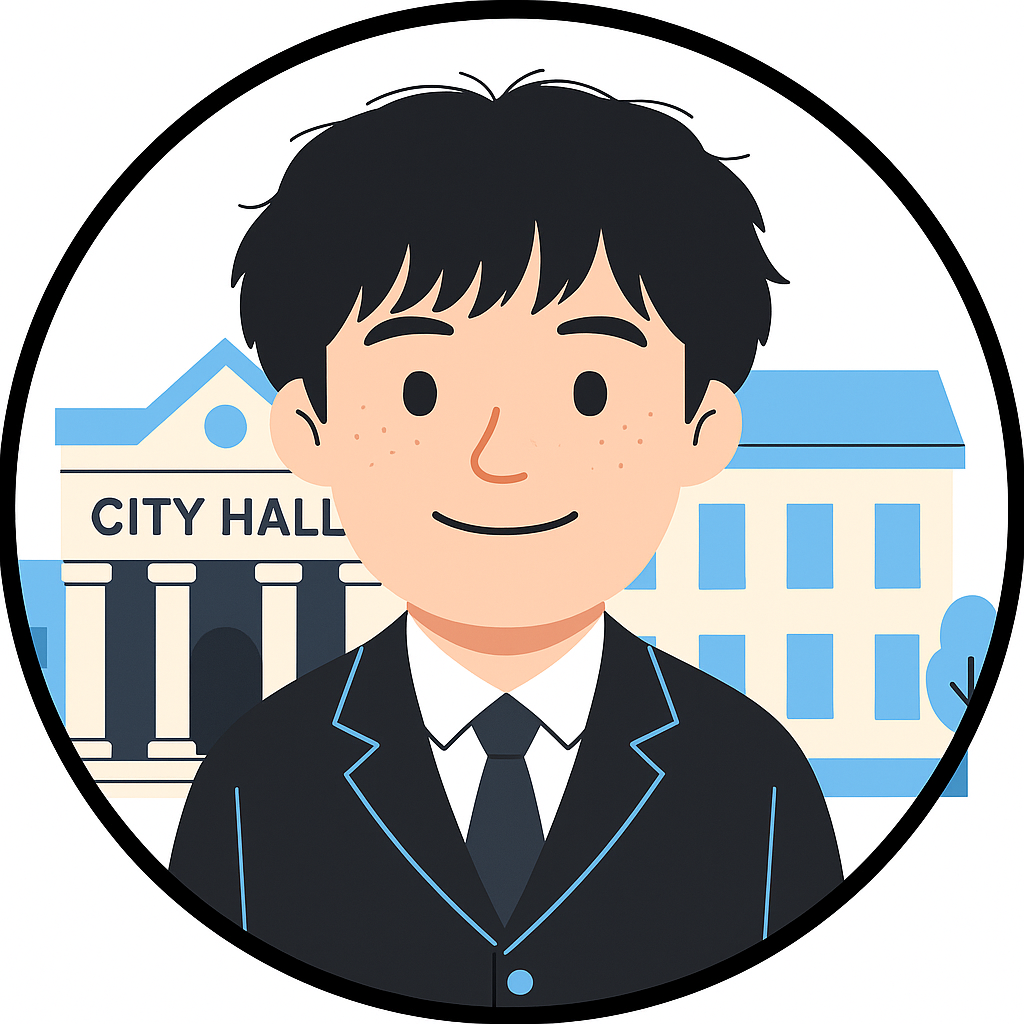
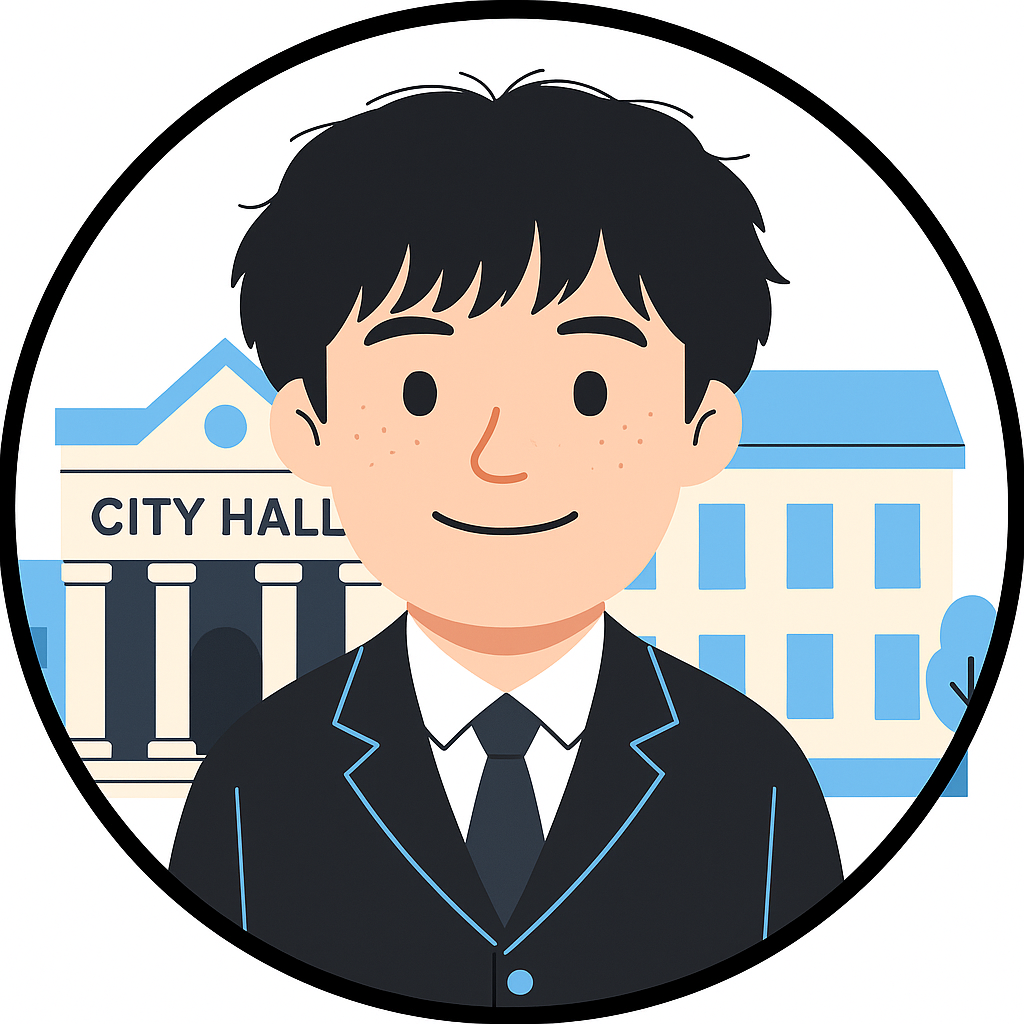
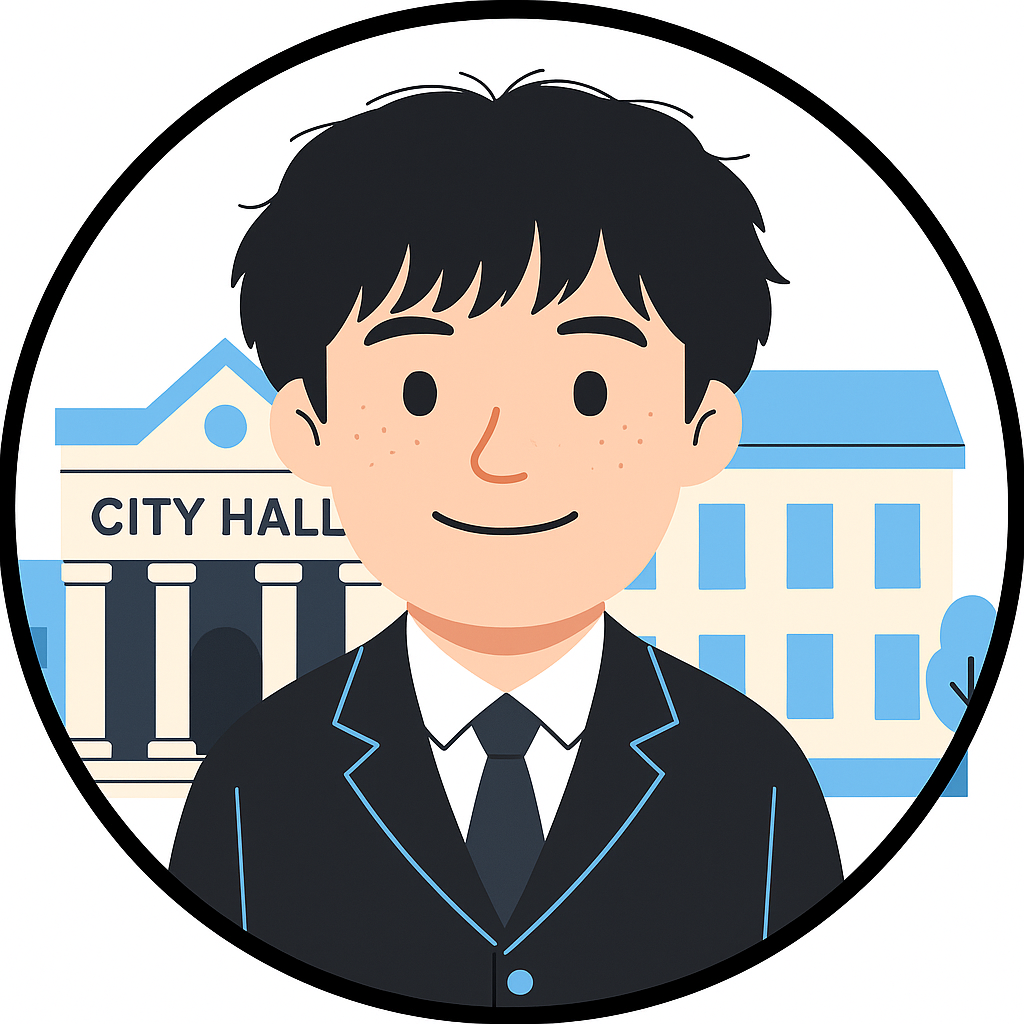
受験者数の増加は倍率を高くするため、「受けやすい ≠ 受かりやすい」ということをおさえておきましょう!
市役所試験の対策には、筆記試験だけでなく、新しい試験形式への対応も必要です。
事前に受験する市役所の試験内容をしっかり調べ、幅広い準備をしましょう。
市役所試験の科目
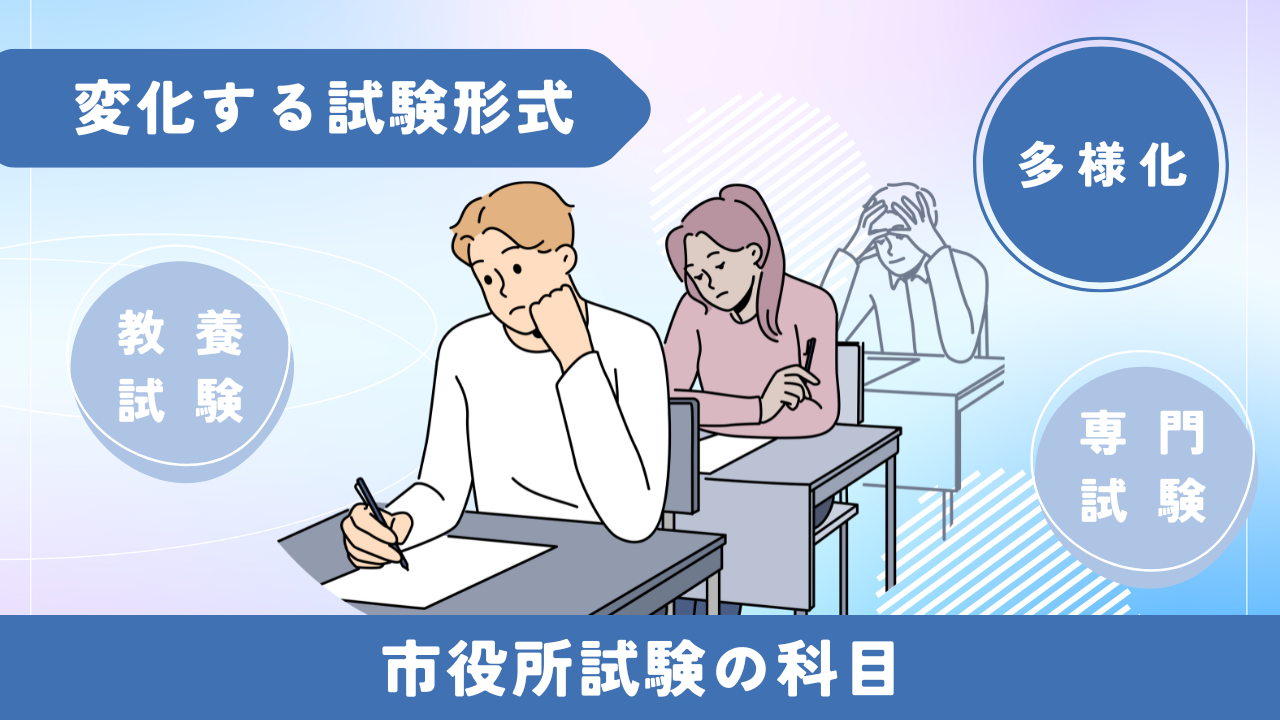
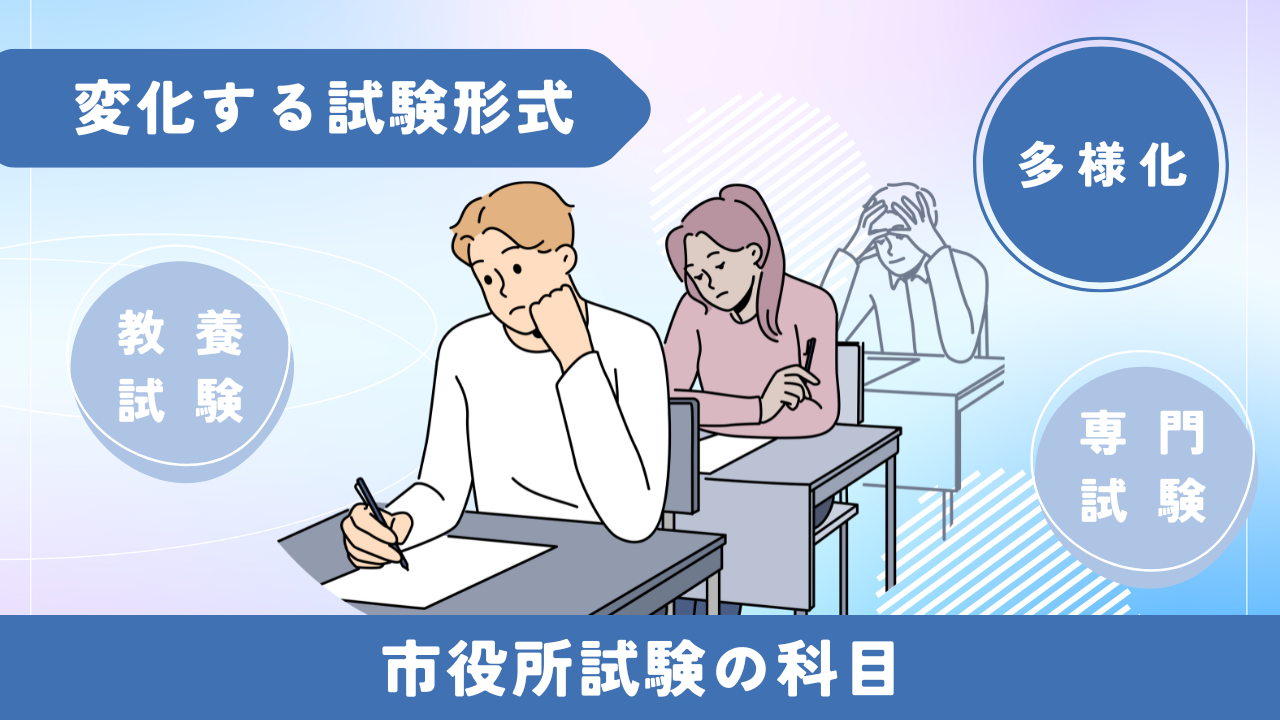



どんな試験科目があるの?
試験科目は大きく分けて「教養試験・専門試験」があり、市役所によって内容が異なります。
さらに近年、試験の形式が変化しつつあります。
それぞれの特徴を知り、効率的に対策を進めましょう。
教養試験の科目
教養試験は、一般的な知識や判断力を問う試験です。
市役所の仕事で必要となる基礎的な学力をチェックする問題が出題されます。
| 科目 | 詳細科目 |
|---|---|
| 数的処理 | 判断推理、数的処理、資料解釈 |
| 文章理解 | 英文、現代文 |
| 社会科学 | 法律・政治、経済、社会、時事 |
| 人文科学 | 地理、日本史、世界史 |
| 自然科学 | 生物、化学、物理、地学、数学 |
教養試験の対策には、基本的な勉強に加えて新聞やニュースをチェックする習慣をつけると効果的です。
専門試験の科目
専門試験では、実務に役立つ専門的な知識が問われます。
| 科目 | 詳細科目 |
|---|---|
| 法律系 | 民法、行政法、憲法 |
| 経済系 | 経済学、財政学 |
| 行政系 | 政治学、行政学、社会政策、国際関係 |
法律を使った手続きや経済の知識を活かした予算管理など、市役所の実務に必要な内容になっています。
専門試験の対策には、過去問を活用し、出題傾向を把握することが大切です。
多様化による影響
近年は、市役所試験の内容が多様化しており、筆記試験だけでなく、新しい形式の試験が増えています。
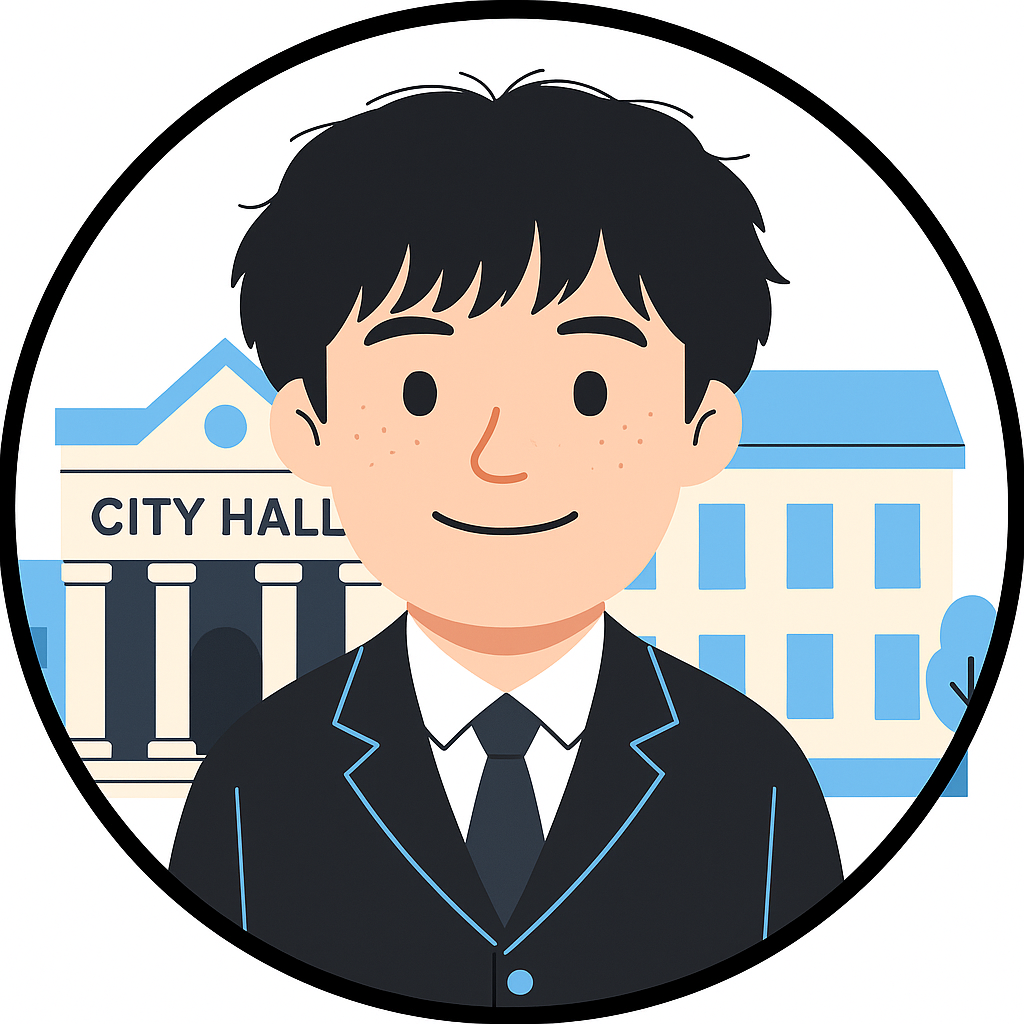
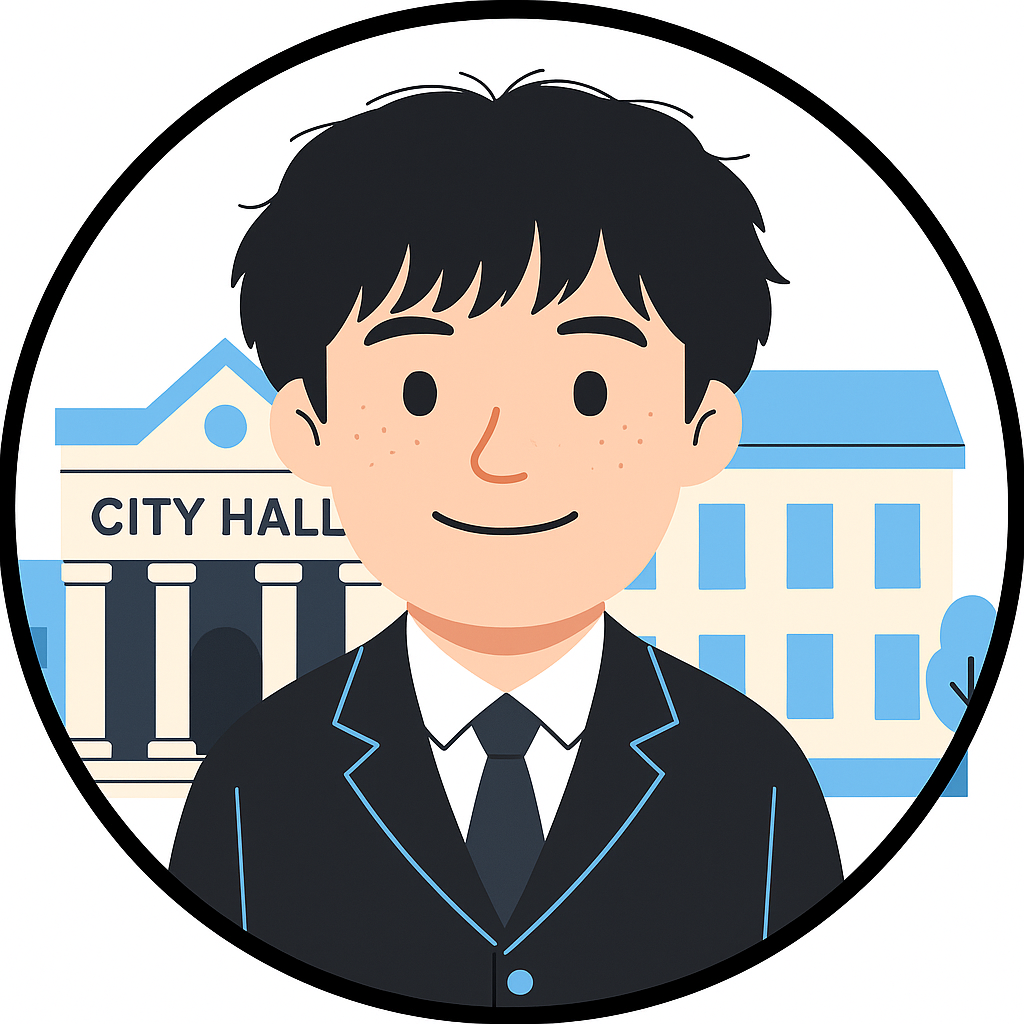
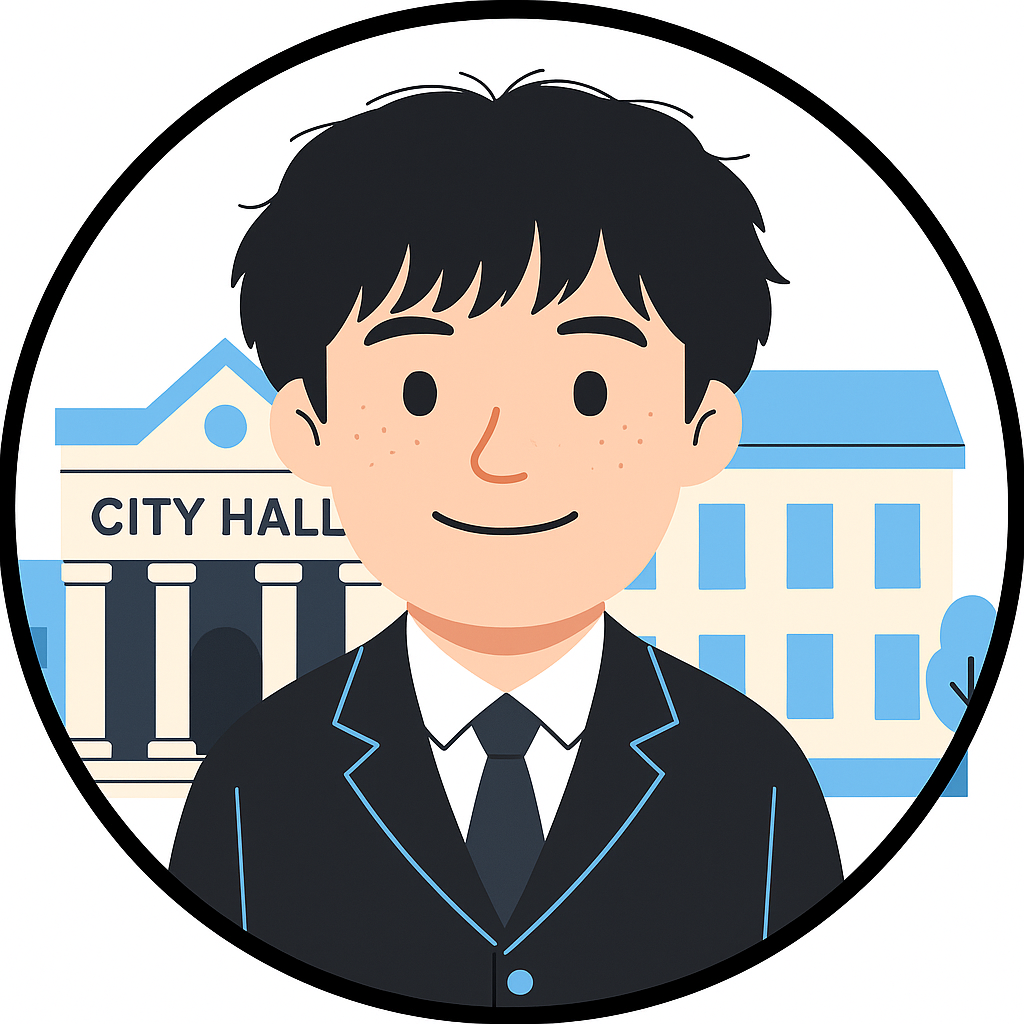
従来の教養試験・専門試験に加え、実践的なスキルを評価する試験が取り入れられています。
| 試験例 | 試験内容 |
|---|---|
| SPI・SCOA | 能力検査、性格検査 |
| グループワーク | テーマ(時事的な話題や市の課題など)に沿ったグループワーク |
| プレゼンテーション | 自己PRや課題に対する解決策の提示などテーマに沿ったプレゼンテーション |
試験の多様化に対応するためには、筆記試験の勉強だけでなく、コミュニケーション力を意識した対策も必要です。
試験スケジュールと準備
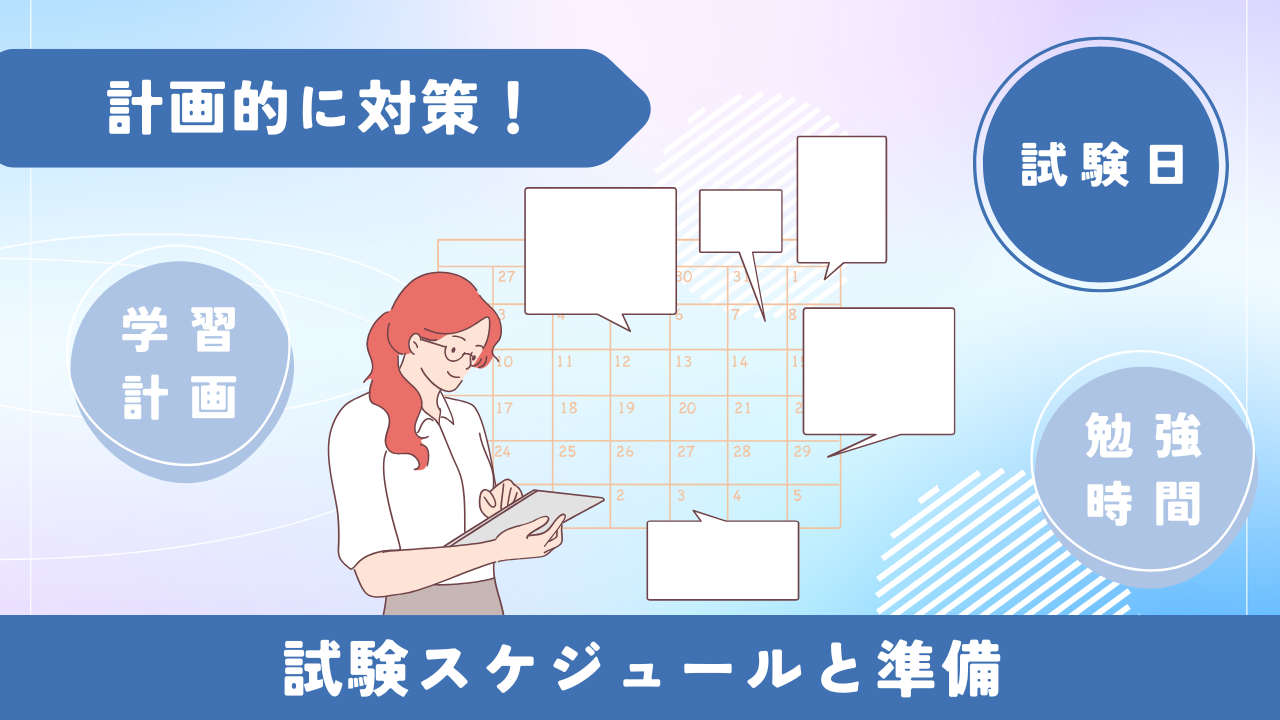
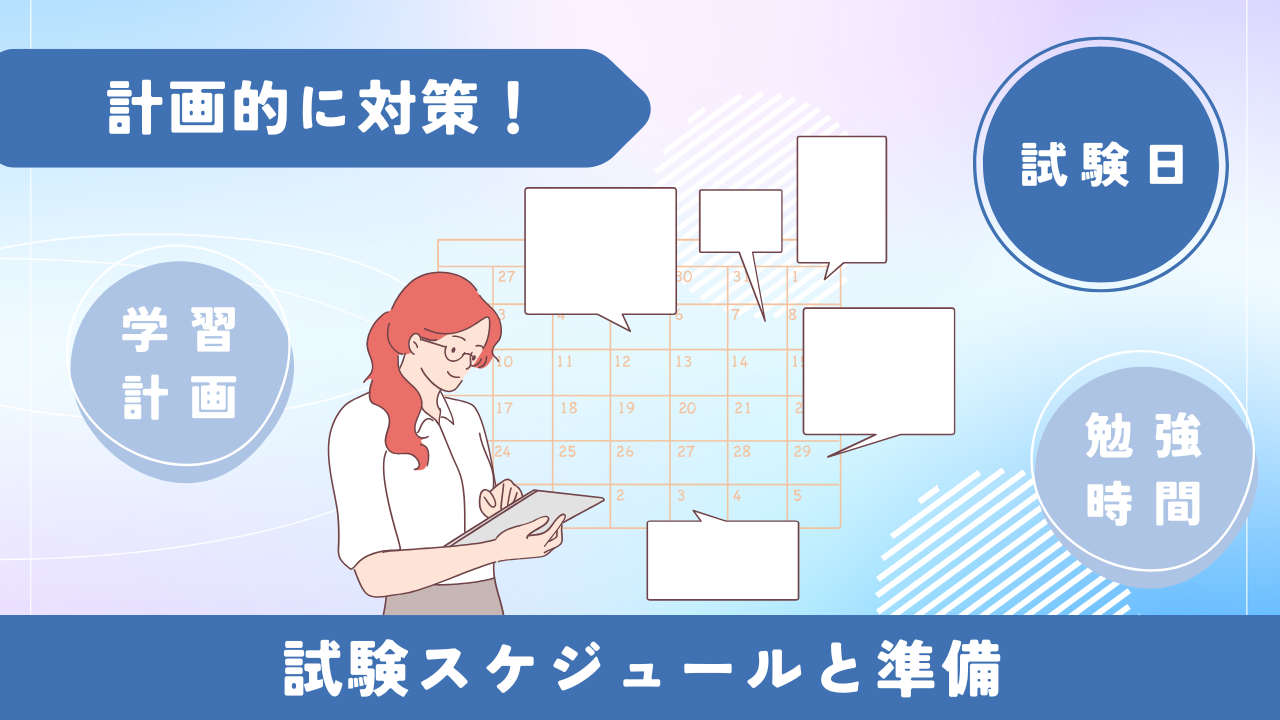



どんなスケジュールで対策すればいいの?
市役所試験に合格するためには、試験の日程をしっかり把握し、計画的に準備を進めることが大切です。
試験スケジュール
市役所試験は、A~D日程に分かれており、市役所ごとに試験日が異なります。
どの日程で受験するかを早めに決め、申し込みを忘れないようにしましょう。
日程によって試験の時期や内容が異なるため、スケジュールを把握しておかないと、受験のチャンスを逃してしまう可能性があります。
また、複数の市役所を受験したい場合、日程が重ならないように調整することが重要です。
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| A日程 (6~7月) | 東京都や政令指定都市などの大きな市役所が中心。 試験科目が多く、倍率も高い傾向にある。 |
| B日程 (7~8月) | 中規模の市役所が多く実施。 A日程と重ならないため、併願する人も多い。 |
| C日程 (9~10月) | 比較的小規模な市役所で実施されることが多い。 試験内容が独自のものになる場合もある。 |
| D日程 (10~12月) | 一部の市役所が実施。 募集人数が少なく、追加募集的な意味合いが強いこともある。 |
試験日程が違うだけでなく、市役所ごとに試験の内容や倍率がちがうため、事前にしっかりリサーチすることが大切です。
受験のチャンスを増やすためにも、A~D日程の特徴を理解し、どの市役所を受けるか計画的に決めましょう。
募集要項を早めにチェックし、スケジュール管理を徹底することが大切です。
学習スケジュール
市役所試験に合格するためには、試験日から逆算して計画的に勉強を進めることが大切です。
必要な勉強時間を把握し、自分に合った学習スケジュールを立てましょう。
市役所試験は科目数が多く、効率的に勉強しないと試験までに準備が間に合わないことがあります。
受験までの残り期間と必要な学習時間を考えながら、無理のないスケジュールを作ることが重要です。
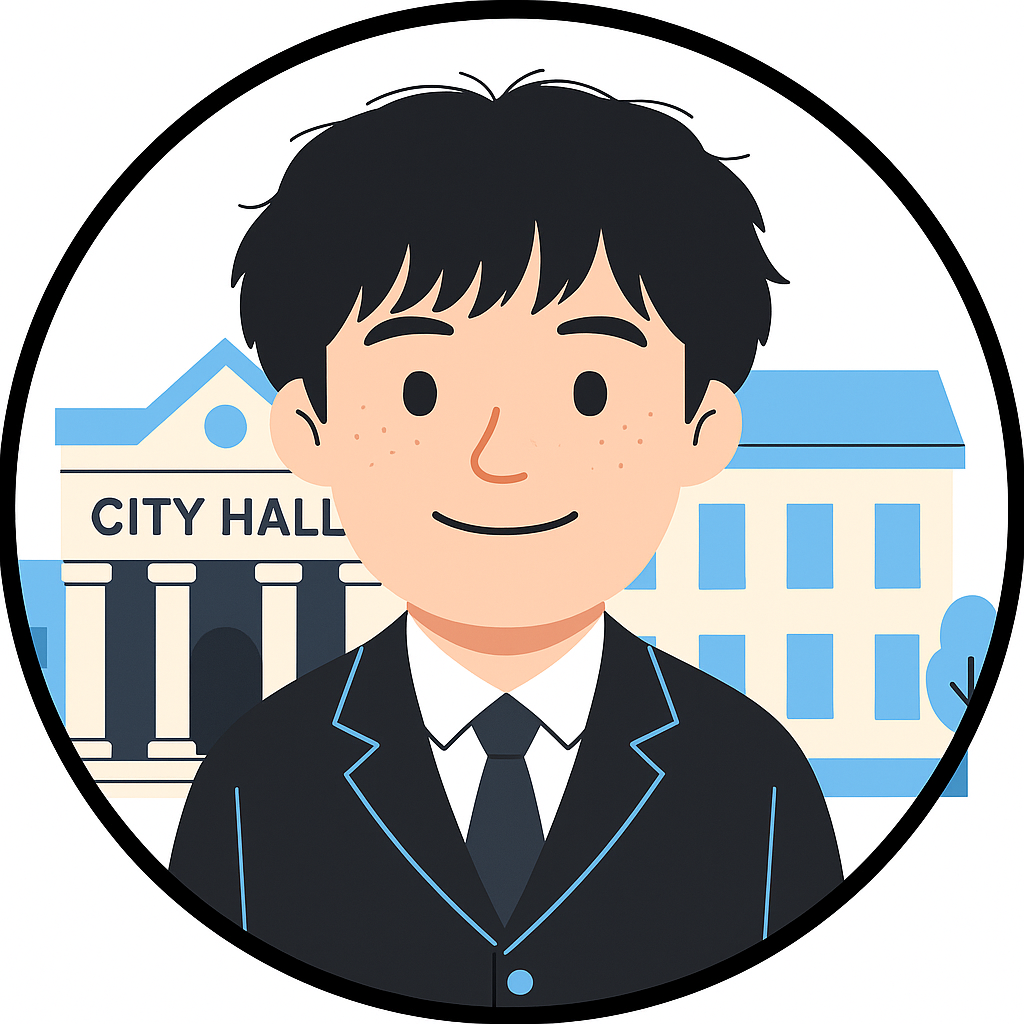
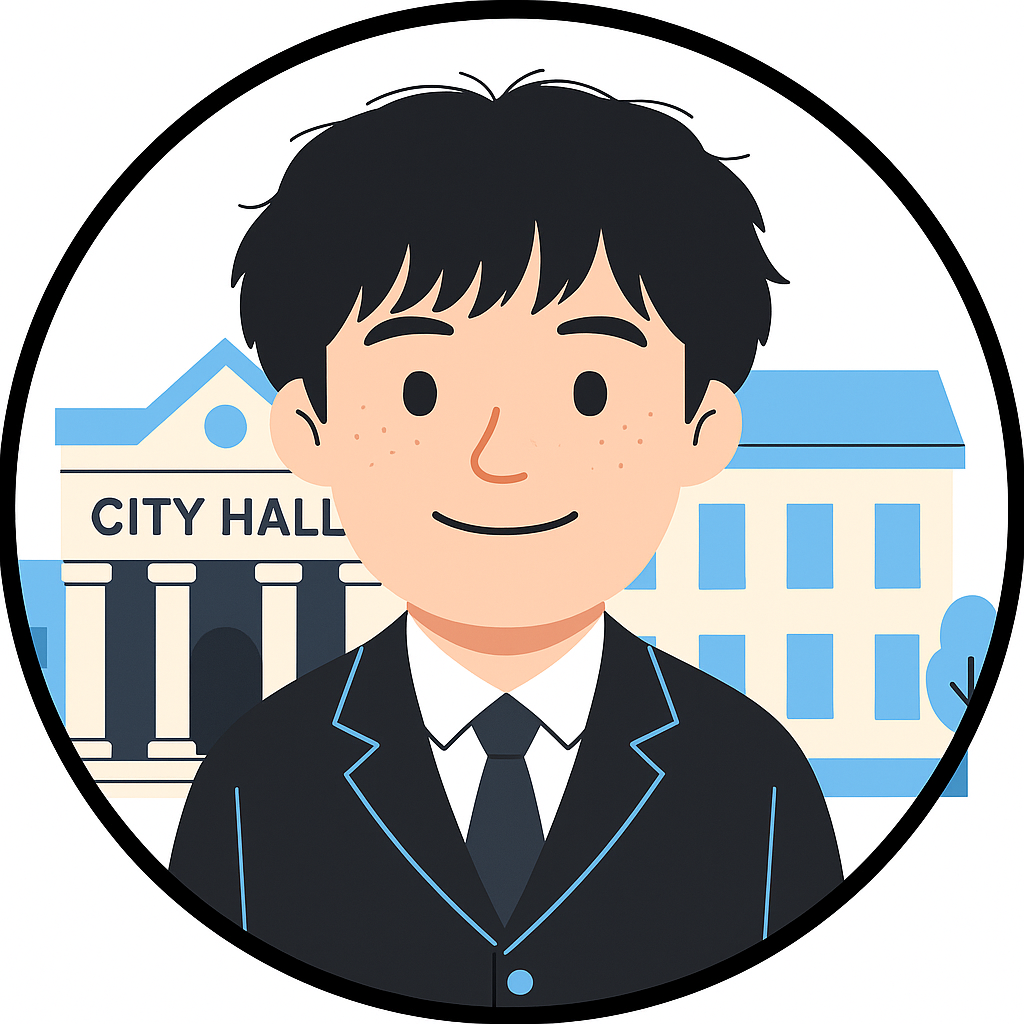
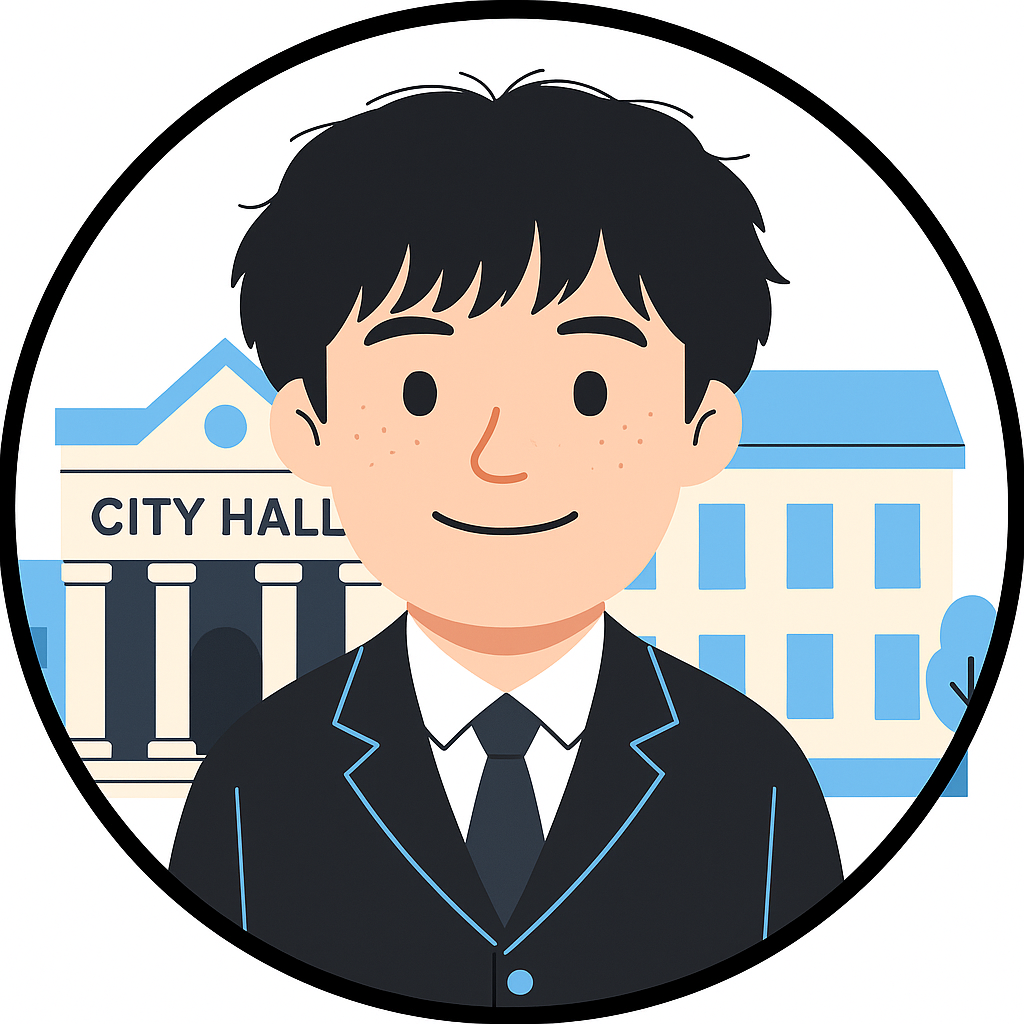
市役所試験に合格するために必要な勉強時間は、500~800時間が目安です。
基礎固め(教養試験・専門試験の基本を学ぶ)
応用学習(過去問や模擬試験に挑戦する)
仕上げ(苦手科目の克服・面接対策・論文対策)
たとえば、平日は2時間、休日は4時間勉強する場合、6か月間で約600時間確保できます。
市役所試験の勉強には時間がかかるため、試験日から逆算して学習計画を立てることが大切です。
自分の生活スタイルに合わせて、無理なく継続できるスケジュールを作りましょう。
科目別対策ポイント





試験対策のコツってある?
市役所試験では、各科目ごとに効果的な対策があります。。
教養試験、専門試験、面接など、それぞれの特徴を知り、正しい方法で勉強を進めましょう。
教養試験対策
教養試験では、出題数が多い科目を中心とした対策が必要です。
教養試験は幅広い分野から出題されるため、効率的に勉強しないと時間が足りなくなります。
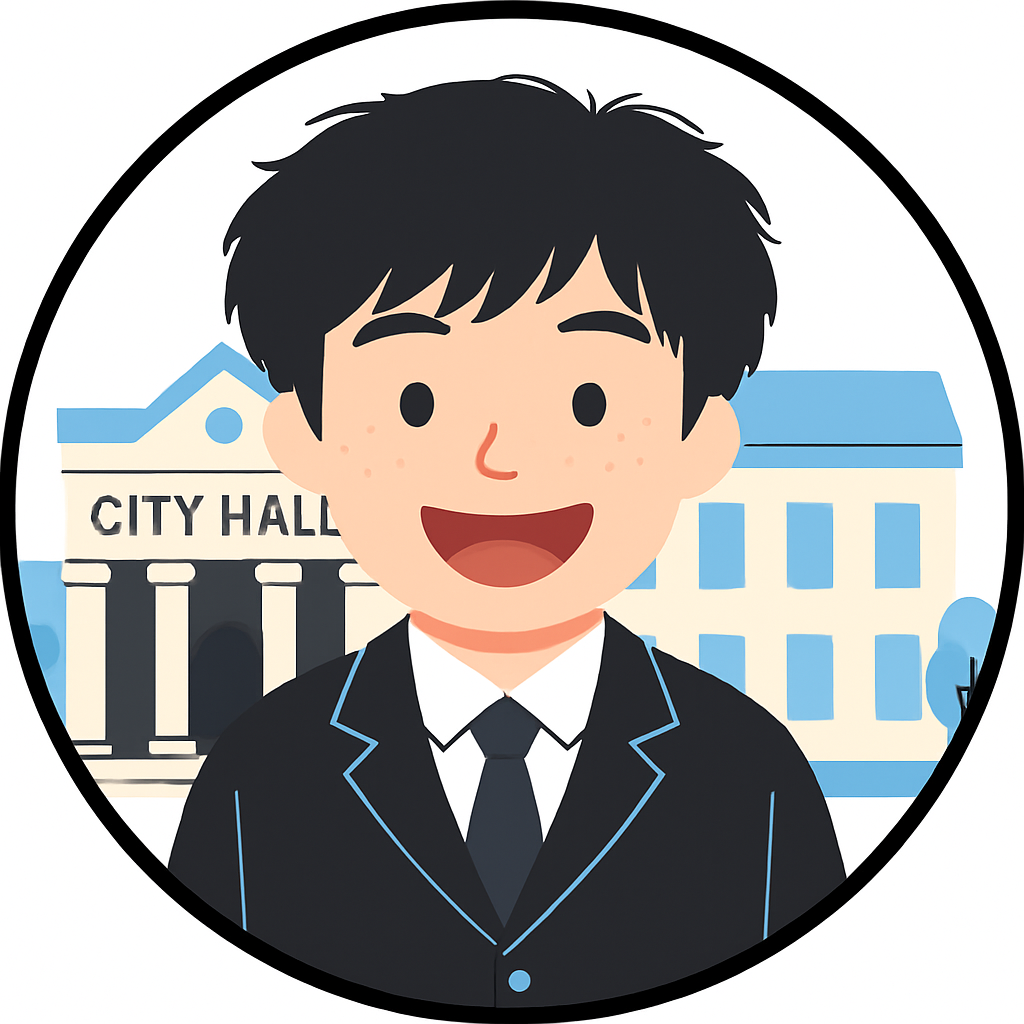
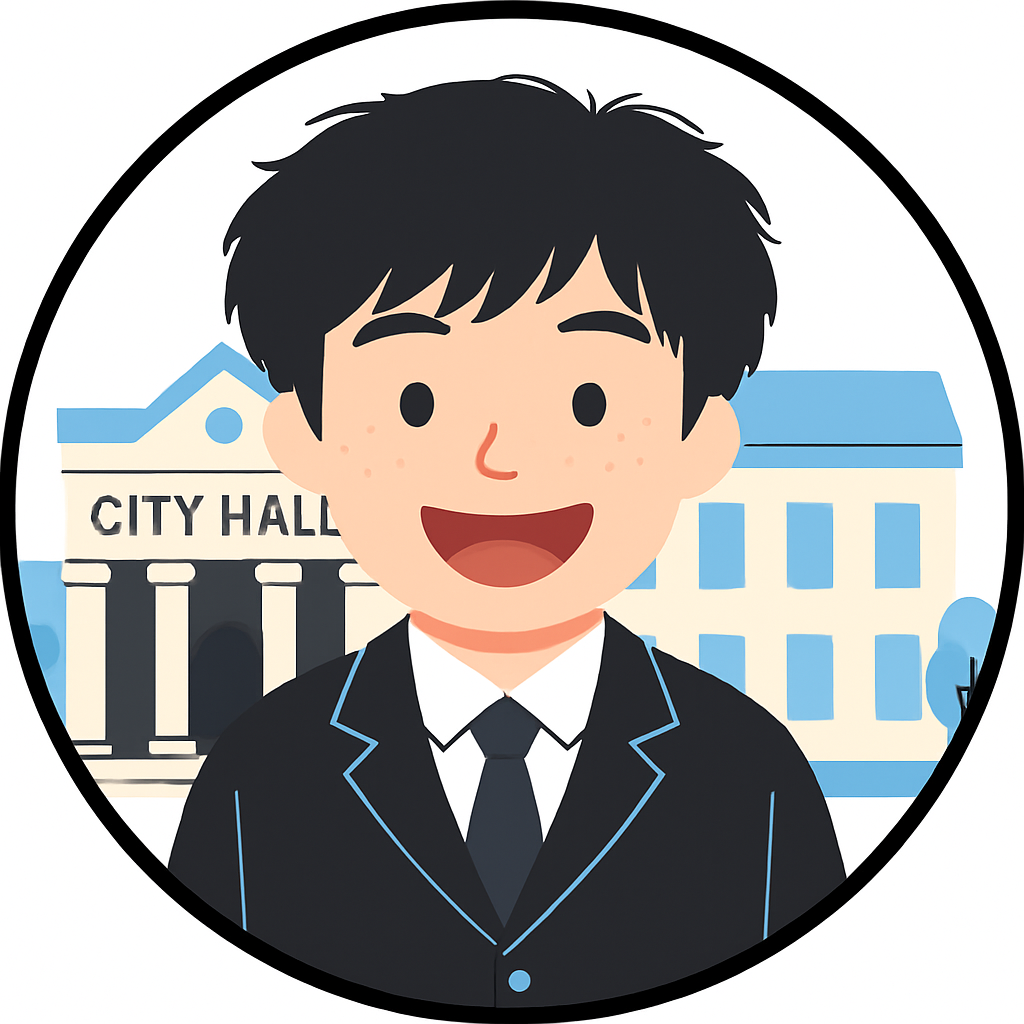
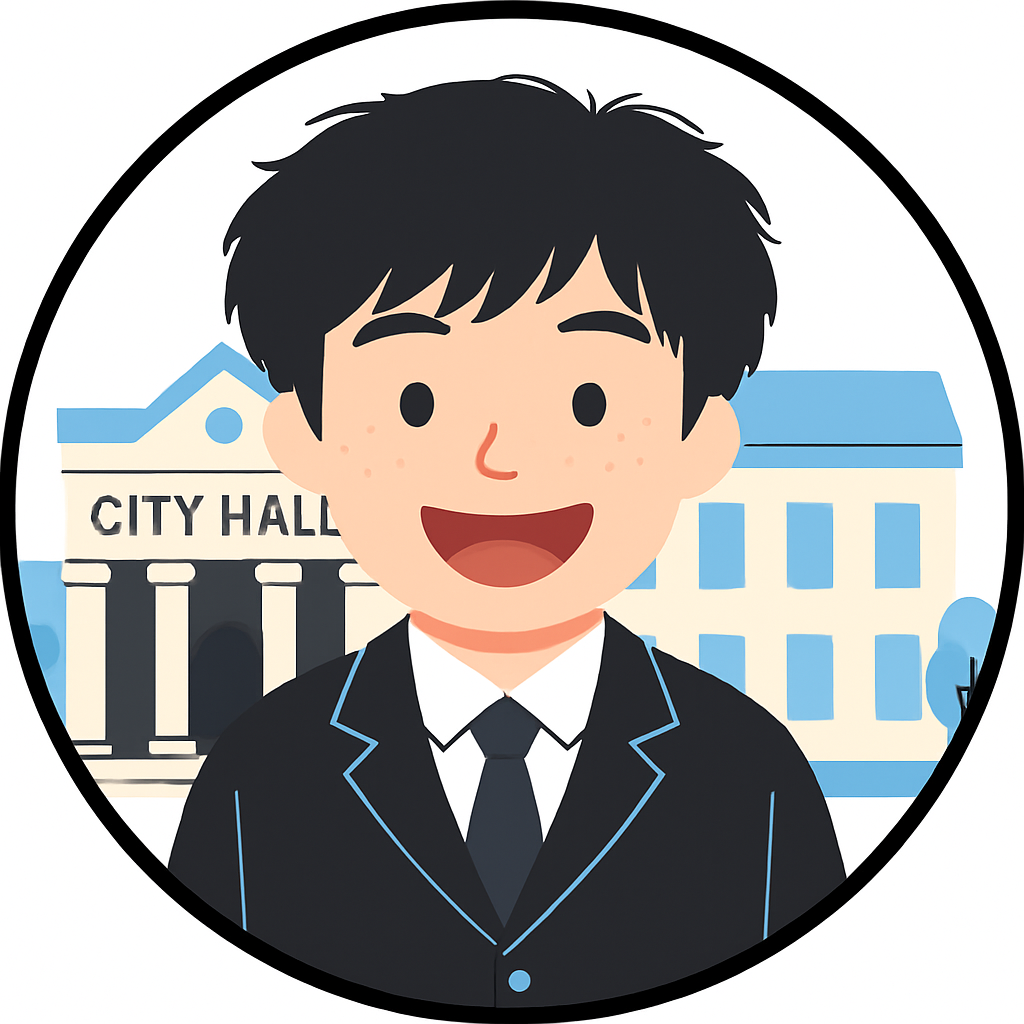
全科目を均等に学ぶのではなく、得点しやすい科目を中心に対策することが大切です。
- 数的推理や判断推理はパターンを覚えることで短期間でも得点が伸びやすい。
- 社会や自然科学は出題範囲が広いので、頻出テーマを優先的に学ぶのが効率的。
教養試験は、限られた時間の中で出題数が多い科目を重点的に学習することが大切です。
過去問を活用しながら実践的な力を身につけましょう。
専門試験対策
専門試験では、出題頻度が多い分野を計画的に学習すれば点がとれます。
教養試験よりも特定の科目に絞られているため、頻出分野を重点的に学べば、短期間でも得点力を上げやすいのが特徴です。
| 科目 | 頻出分野例 |
|---|---|
| 法律系 | 憲法:人権、統治機構 民法:契約、債権 |
| 経済系 | 経済学:需要と供給、GDPの計算 |
基礎を固め、過去問を活用しながら実践力を高めましょう!
面接対策
市役所の面接には、事前準備が必要不可欠です。
事前に想定質問を考え、練習しておくことで、落ち着いて分かりやすく話せるようになります。
過去の経験を振り返り「なぜ市役所で働きたいのか」「自分の強みをどう活かせるか」を整理。
「市役所の業務で興味がある分野は?」「仕事で大切にしたいことは?」などの質問を想定し、具体的なエピソードを交えて回答を準備。
家族や友人と模擬面接を行い、本番の雰囲気に慣れておくことで、自信を持って話せるよう練習。
面接では、明確な志望動機と具体的なエピソードを準備することが大切です。
事前準備をしっかり行い、落ち着いて面接に臨みましょう。
オススメの教材と講座
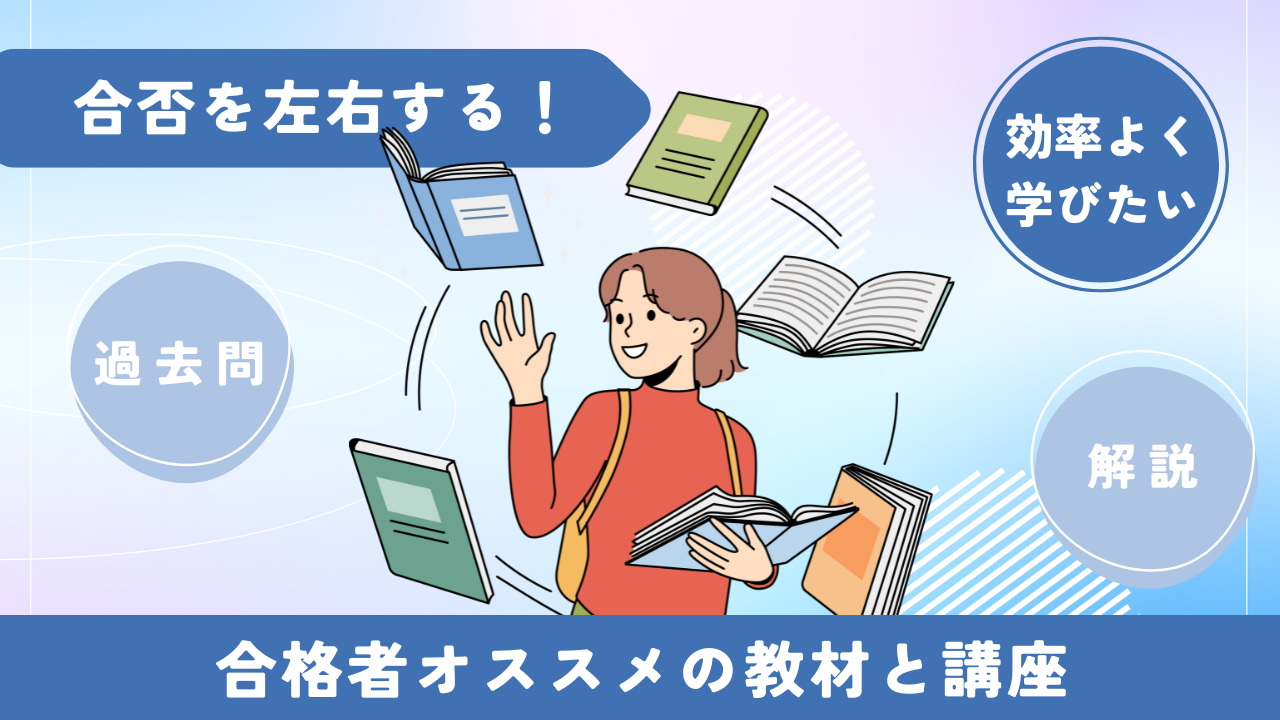
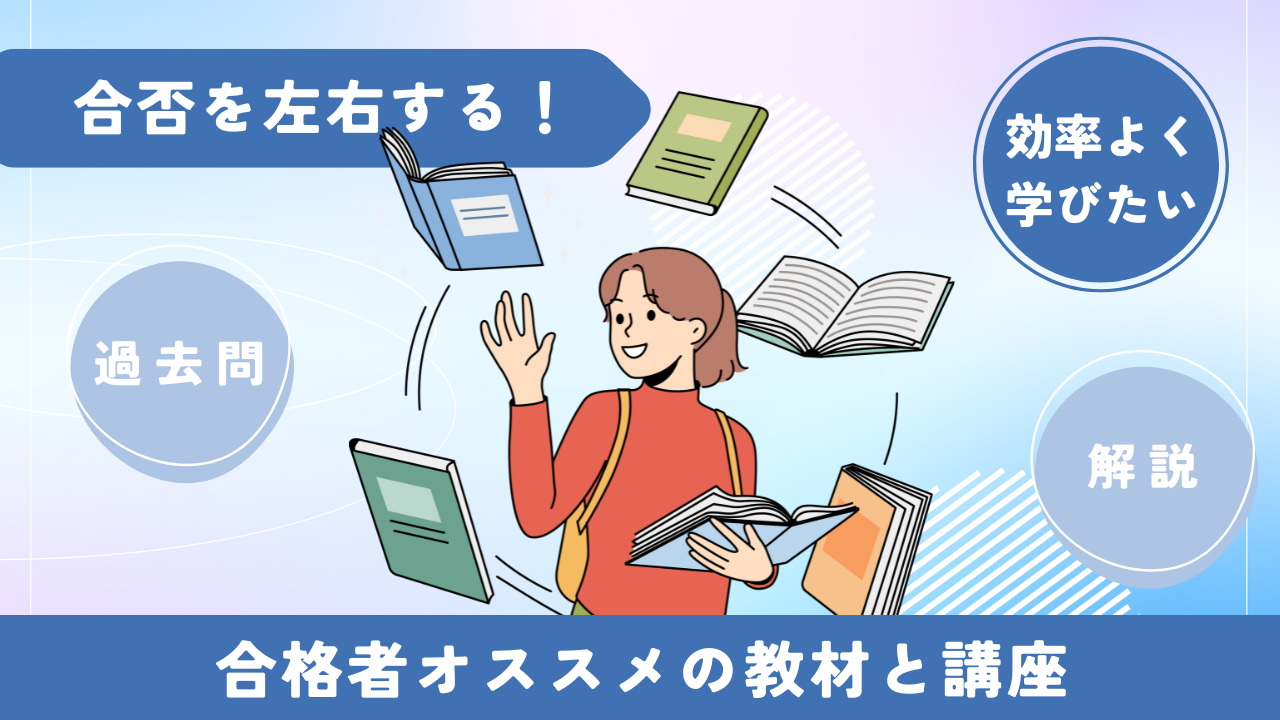



効率よく学べる教材や講座ってあるの?
特に初心者の方は、試験範囲が広いため、どの教材や講座を選ぶかが合否を左右することもあります。
ここでは、市役所試験に特化してオススメな教材と講座について紹介します。
市役所試験に特化した教材
市役所試験向けの教材を選ぶときは、試験範囲を効率よく学べるものを選びましょう。
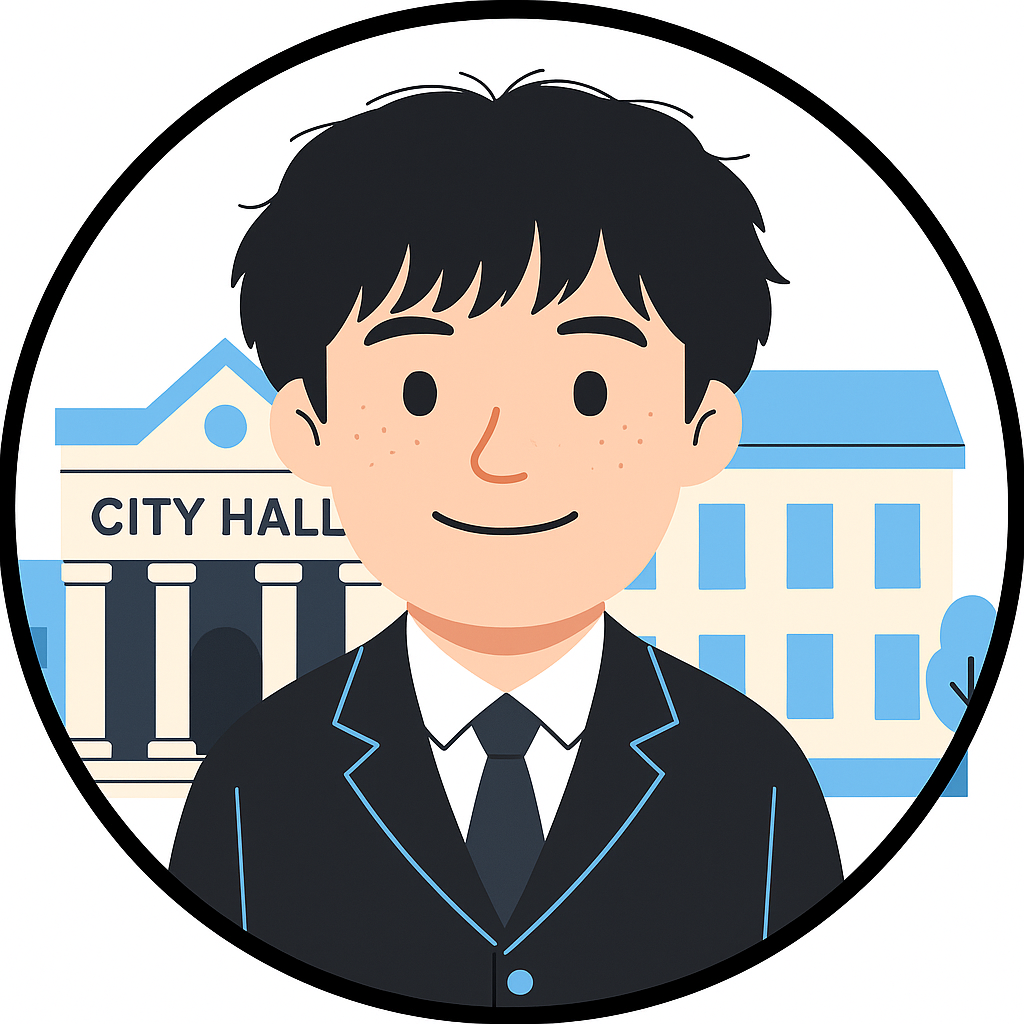
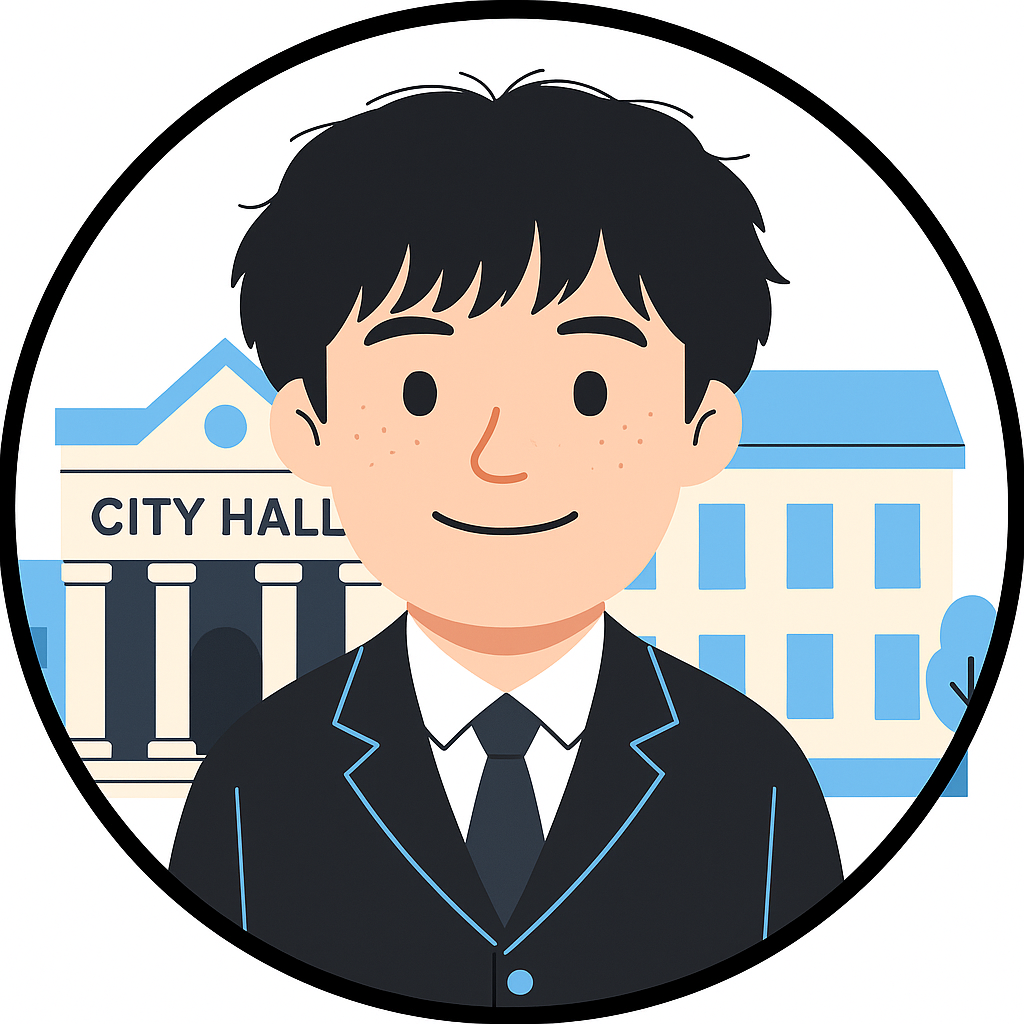
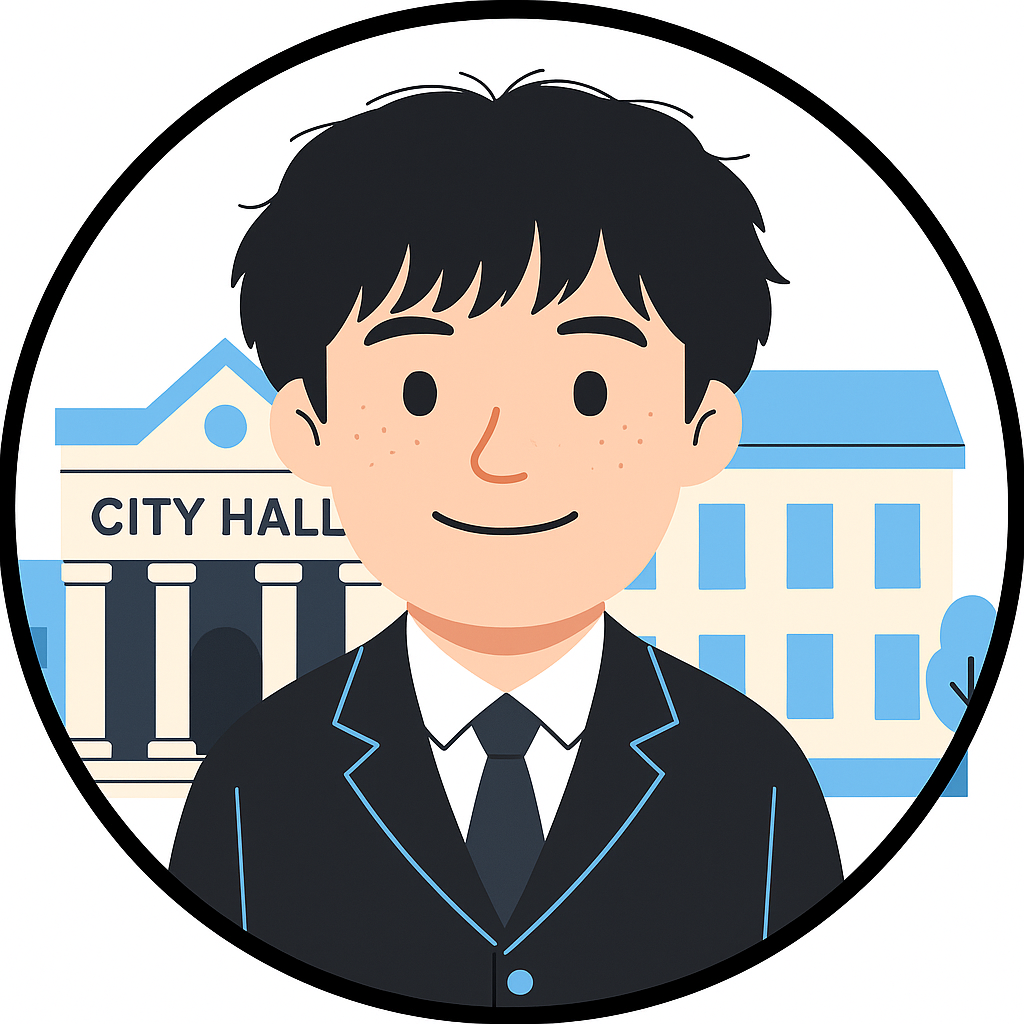
特に、過去問と解説が充実している教材がオススメです。
市役所試験では、教養試験や専門試験など幅広い知識が求められます。
そのため、単なる参考書ではなく、出題傾向を分析し、実際の試験に近い問題を解ける教材を使うことで、合格に近づけます。
たとえば「新スーパー過去問ゼミ」は過去の出題傾向を分析し、重要なポイントを絞って学習できるため、短期間で効率よく対策できます。
また「2026年度版 市役所上・中級 教養・専門試験 過去問500」は実際の試験形式に沿った問題が載っており、本番のシミュレーションに役立ちます。
市役所試験の教材は、試験範囲をカバーしつつ、過去問演習ができるものを選びましょう。
実際の試験に近い問題を解くことで、確実に実力をつけられます。
市役所試験に特化した講座
独学が不安な人や短期間で効率よく学びたい人は、市役所試験に特化した講座をオススメします。
- 市役所試験の範囲は広く、独学で効率よく学習するのが難しい。
- 講座では、出題傾向を押さえたカリキュラムが組まれており、短期間でも効果的に学習できる。
- 模擬試験や個別指導により、自分の弱点を把握しやすい。
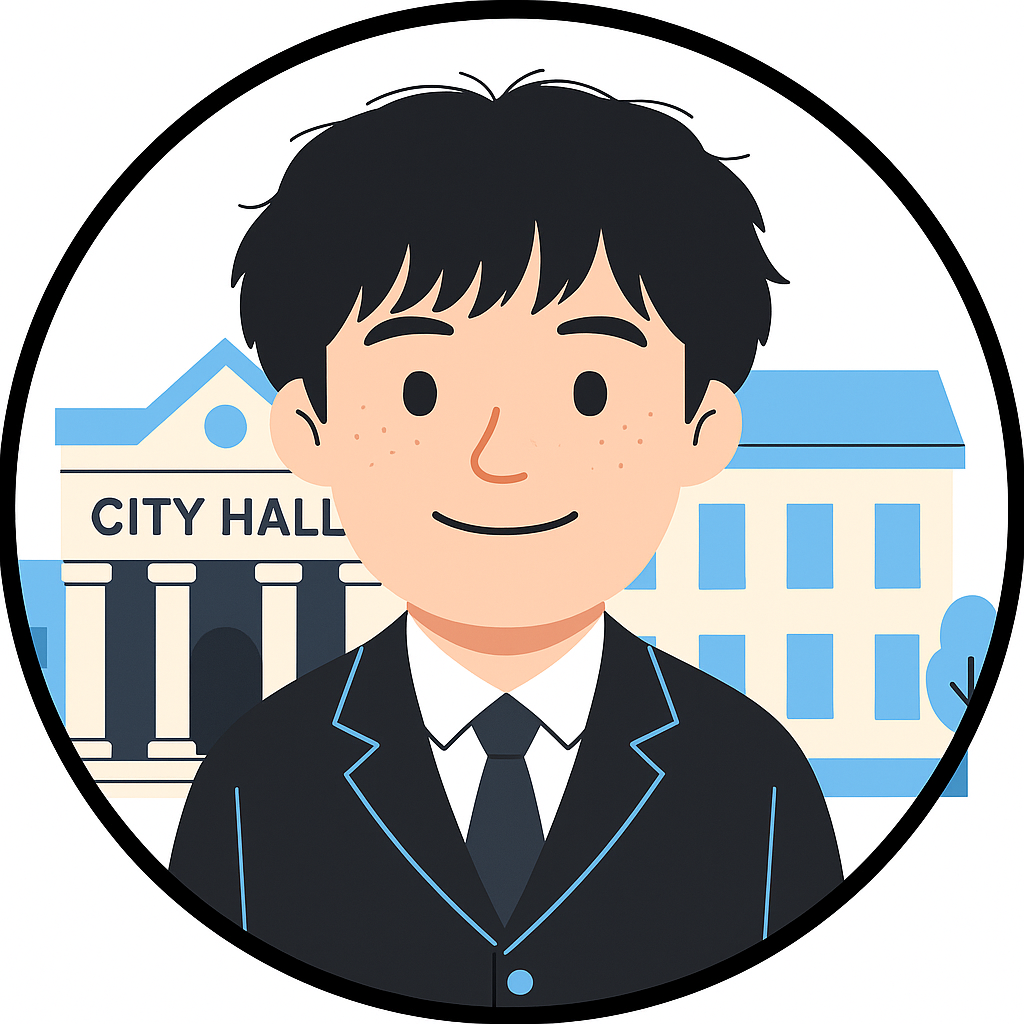
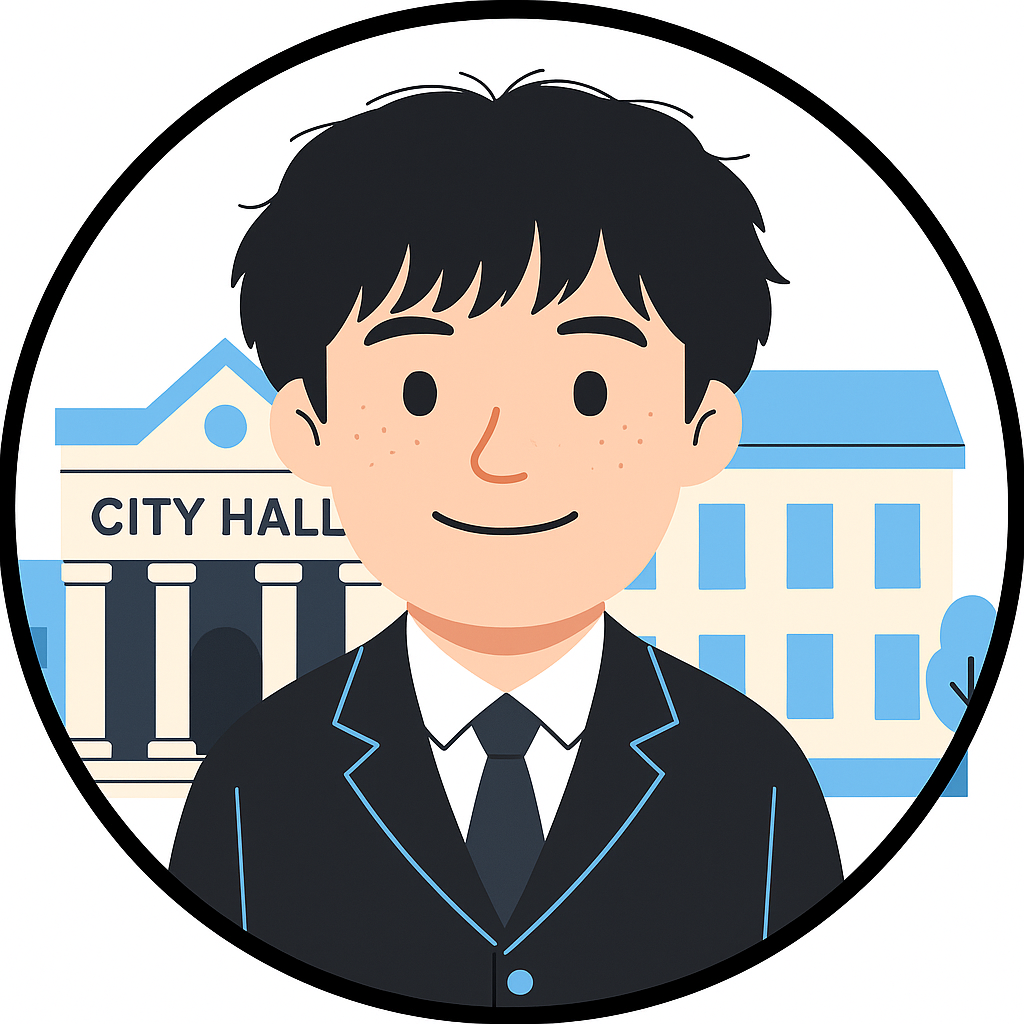
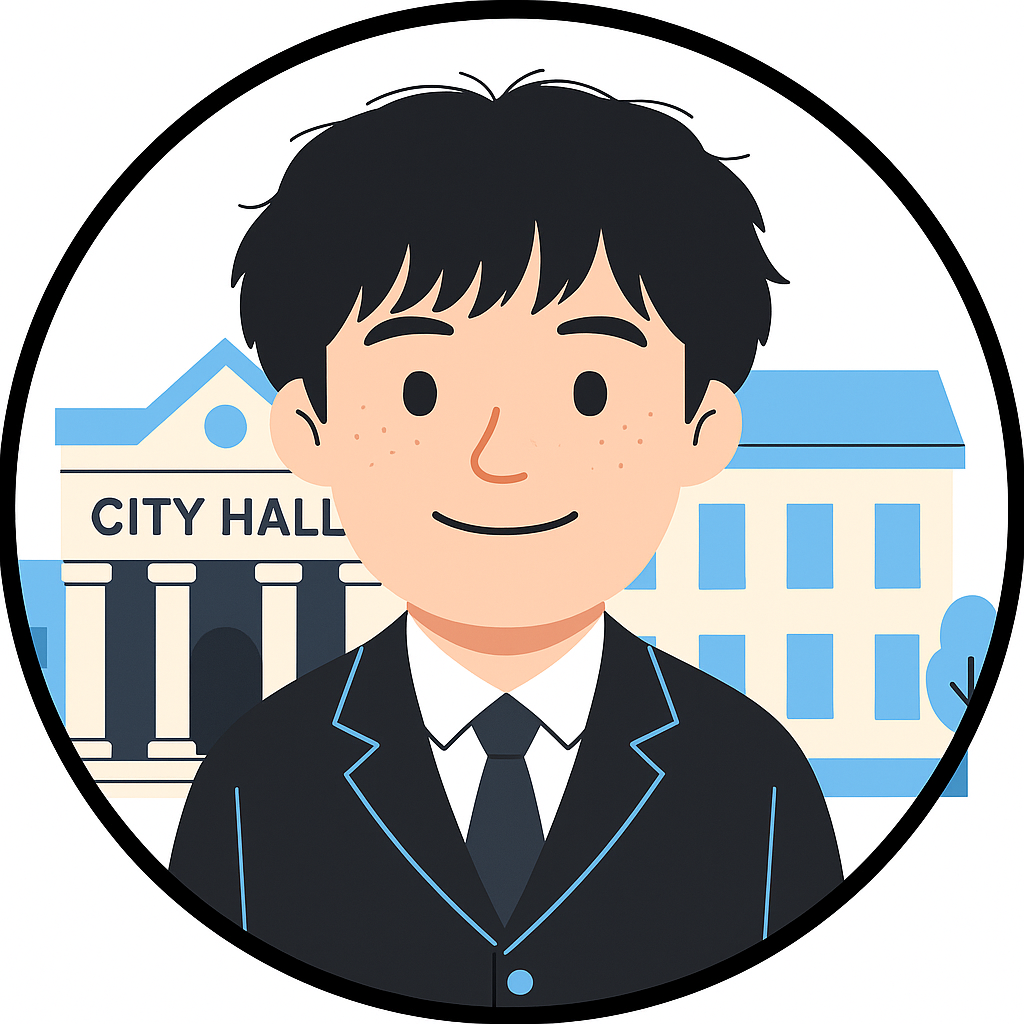
講座を利用すれば、出題傾向の把握や進捗管理にかかる時間を講師にお任せできちゃいます。
たとえば「LEC東京リーガルマインド」は、高い合格実績があり、教材や指導のレベルの高さはもちろん、面接対策などのサポートも充実!
\ 市役所に特化した公務員講座ならLEC /
独学が不安な方や、効率よく学びたい方には、市役所試験専門の講座を活用するのがオススメです。
プロの講師の指導を受けることで、より確実に合格を目指せます。
モチベーション維持法





長続きや継続が苦手でも大丈夫?
市役所試験の勉強は長期間にわたるため、途中でやる気が下がってしまうこともあります。
モチベーションを保つには、市役所で働く魅力や合格後の生活を具体的にイメージすることが大切です。
市役所で働く魅力
市役所で働く魅力は、試験勉強のモチベーションにつながります。
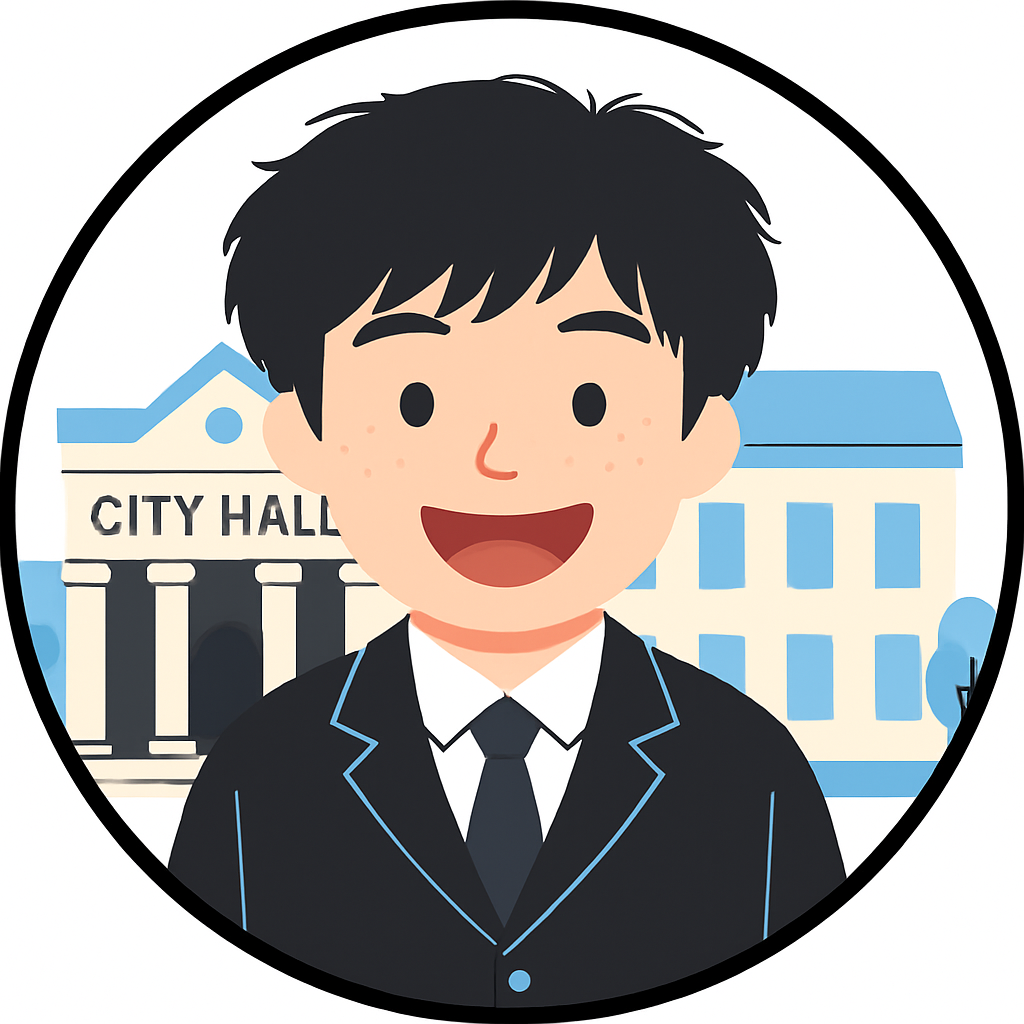
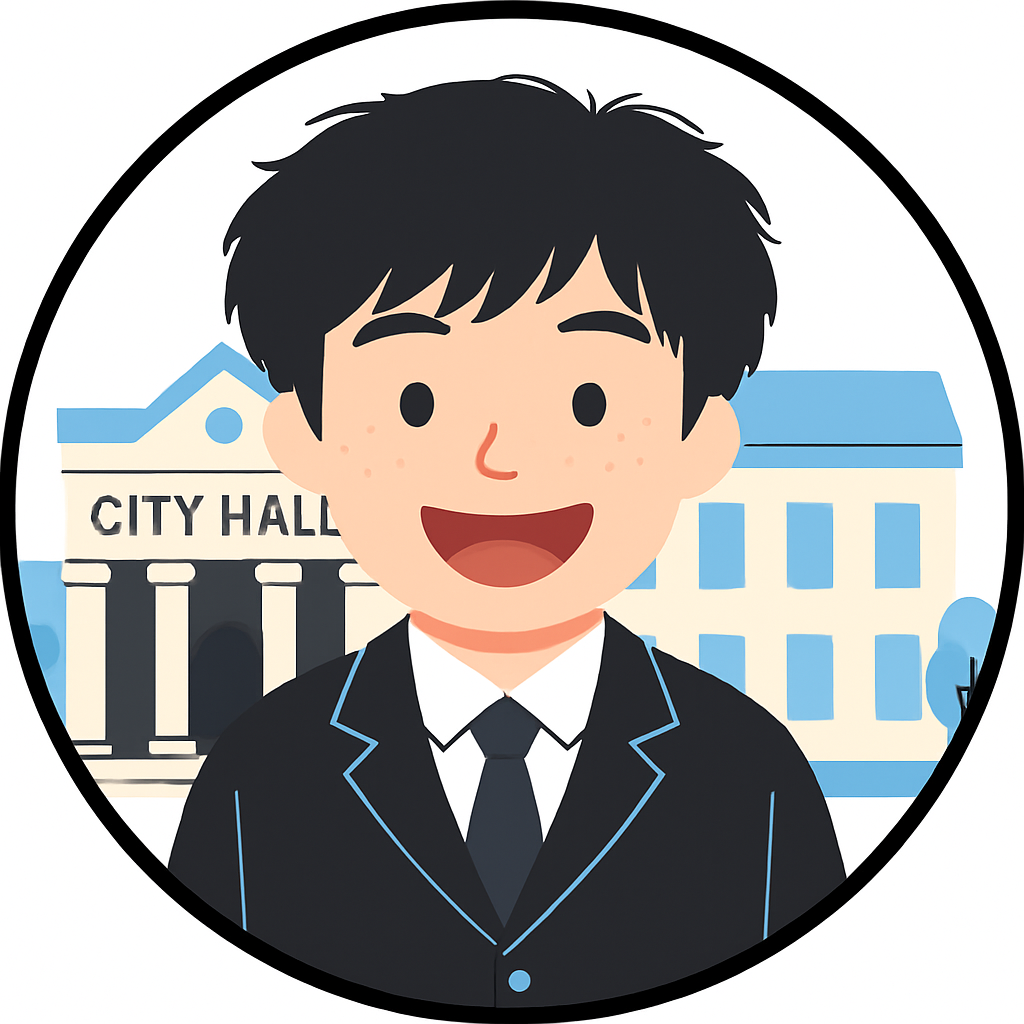
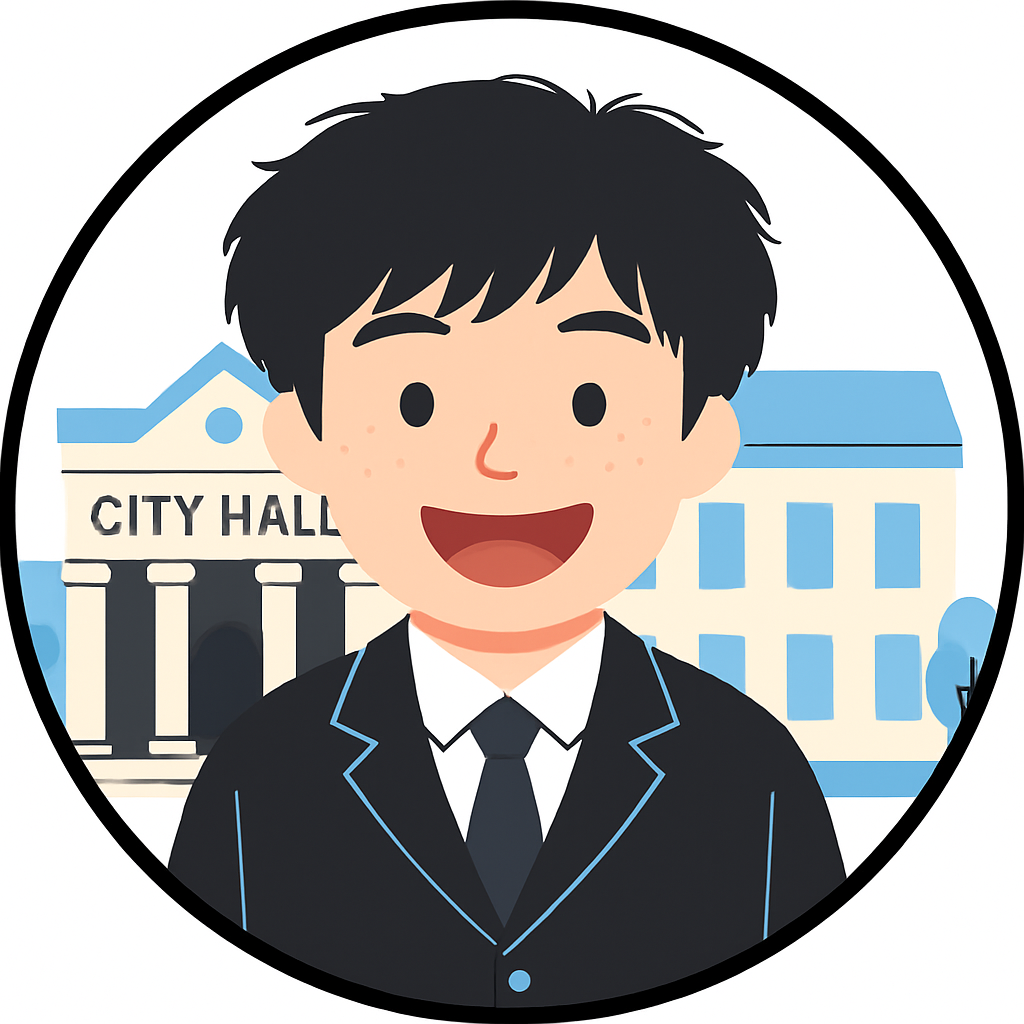
市役所で働く未来を想像することで、やる気を維持しやすくなるからです。
たとえば、公務員は景気に左右されにくく、給与や福利厚生も安定しているため、安定した労働環境を得られます。
安定した職場環境や働きやすい環境は、市役所勤務の大きな魅力です。
試験勉強に疲れたときは、合格後の働く姿を想像しながら、モチベーションを維持しましょう。
現役職員が徹底解説!市役所転職の魅力と後悔しないための対策4選!
プライベートの充実
試験合格で得られるプライベートの充実も、試験勉強のモチベーションにつながります。
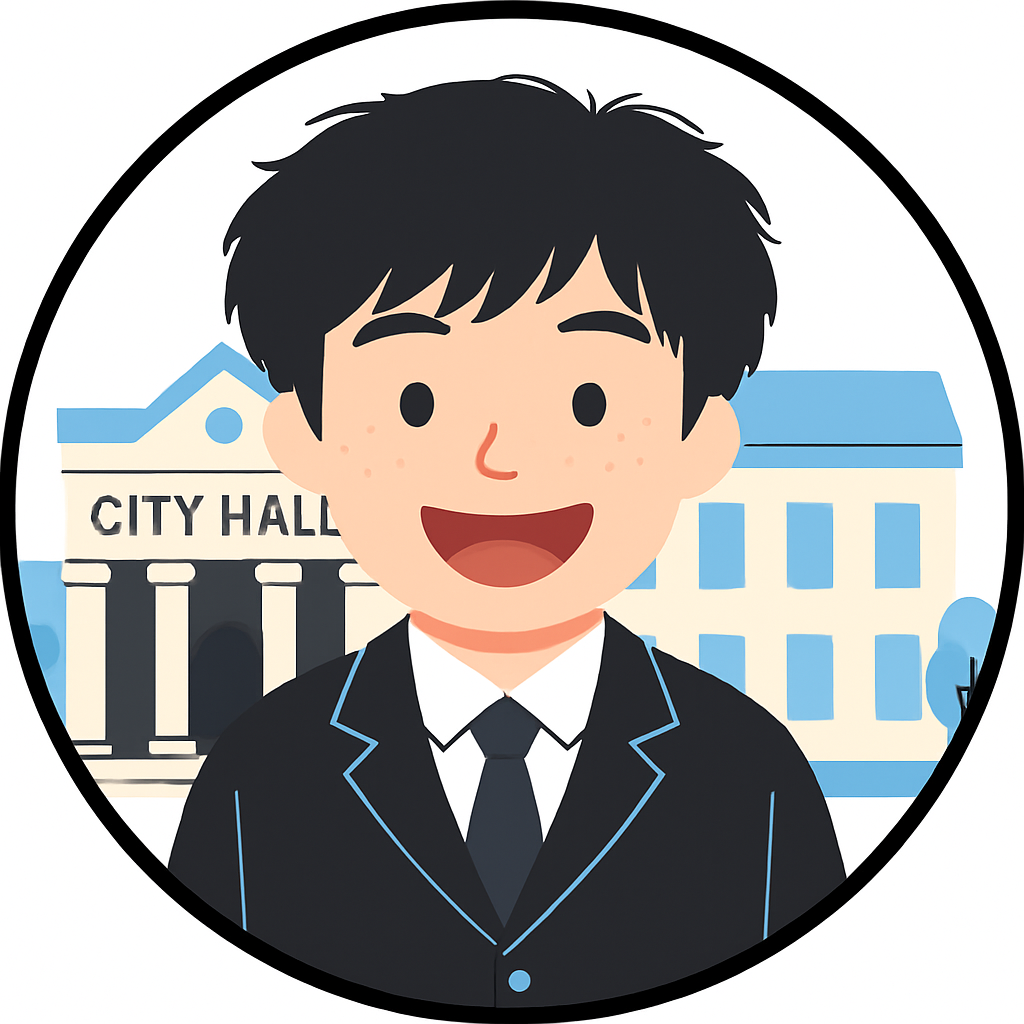
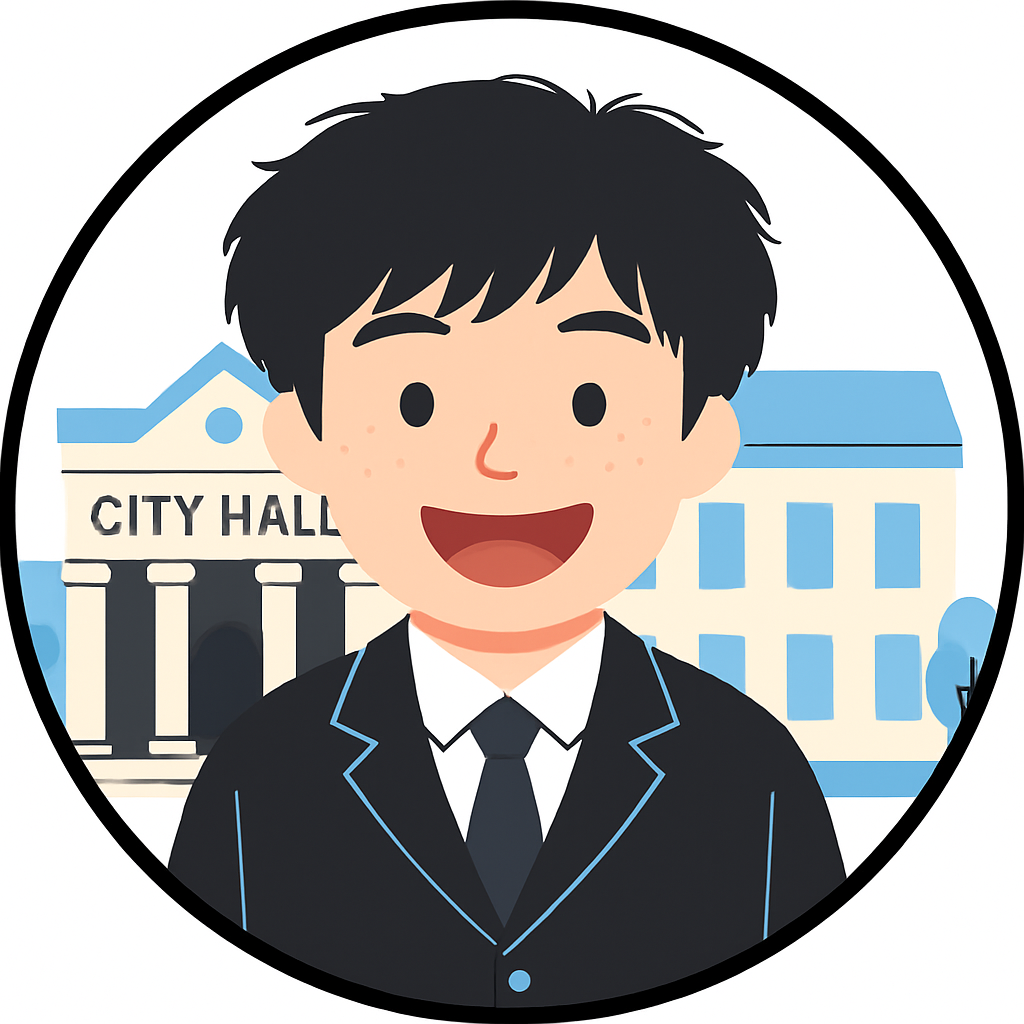
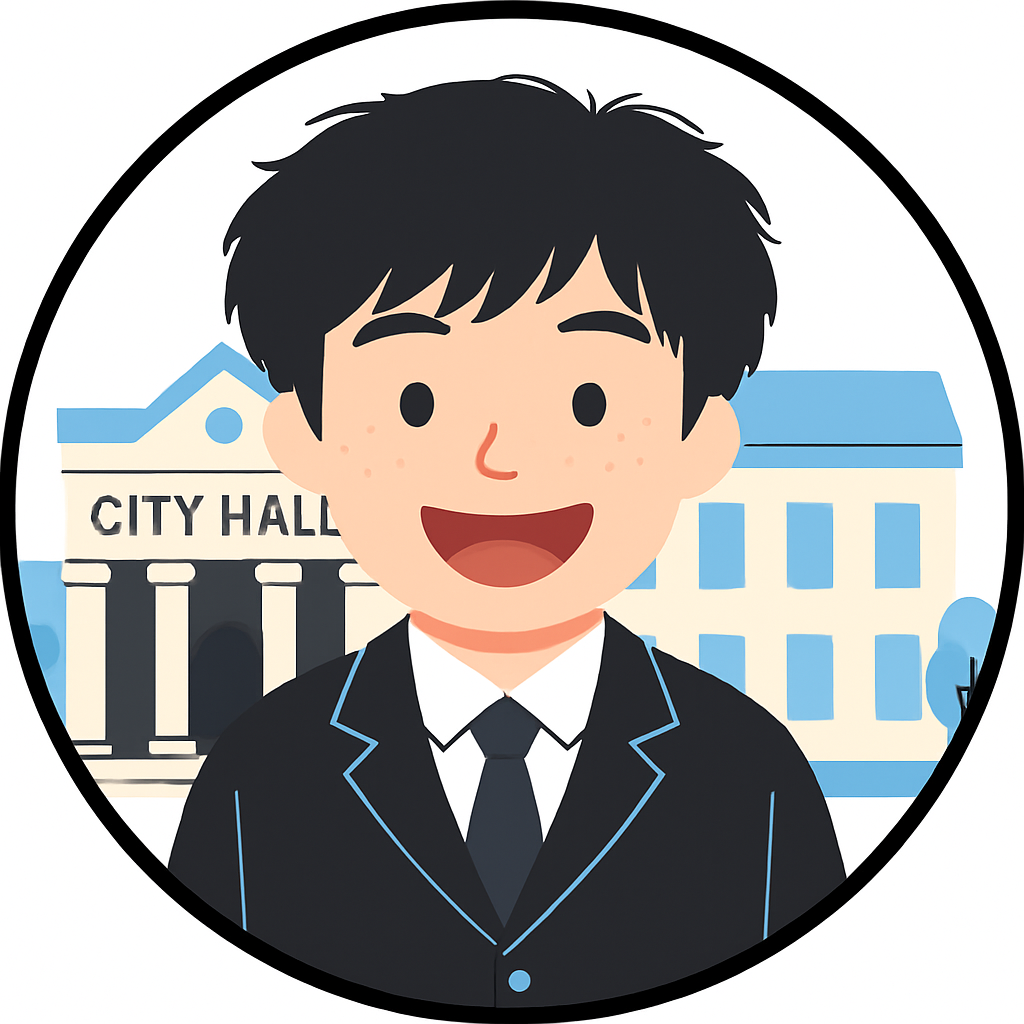
仕事の充実に加えて、プライベートが充実する未来を想像することで、やる気に繋げることができます。
たとえば、市役所は残業が少なく、有給休暇も取りやすい職場が多いため、家族や趣味の時間を確保しやすいです。
また、育児休暇や介護休暇などの制度も整っており、ライフステージに応じた働き方ができます。
ワークライフバランスが取りやすいことは、市役所勤務の大きな魅力です。
試験勉強中も、合格後の働き方をイメージしながら、前向きに取り組みましょう。
【まとめ】計画的・効率的な試験対策


結論、市役所試験には計画的な試験対策が必要です。
試験スケジュールから、幅広い試験範囲を勉強するための時間を逆算して計画することが大切です。
- 市役所試験に合格するには、500~800時間の勉強が必要。
- 科目別の出題傾向を知り、効率的な対策を立てることがコツ。
- 教材・講座選びで、勉強時間を大幅にへらすことができる。
つまり市役所試験では、現実的な計画と効率的な試験対策が合格への近道です。
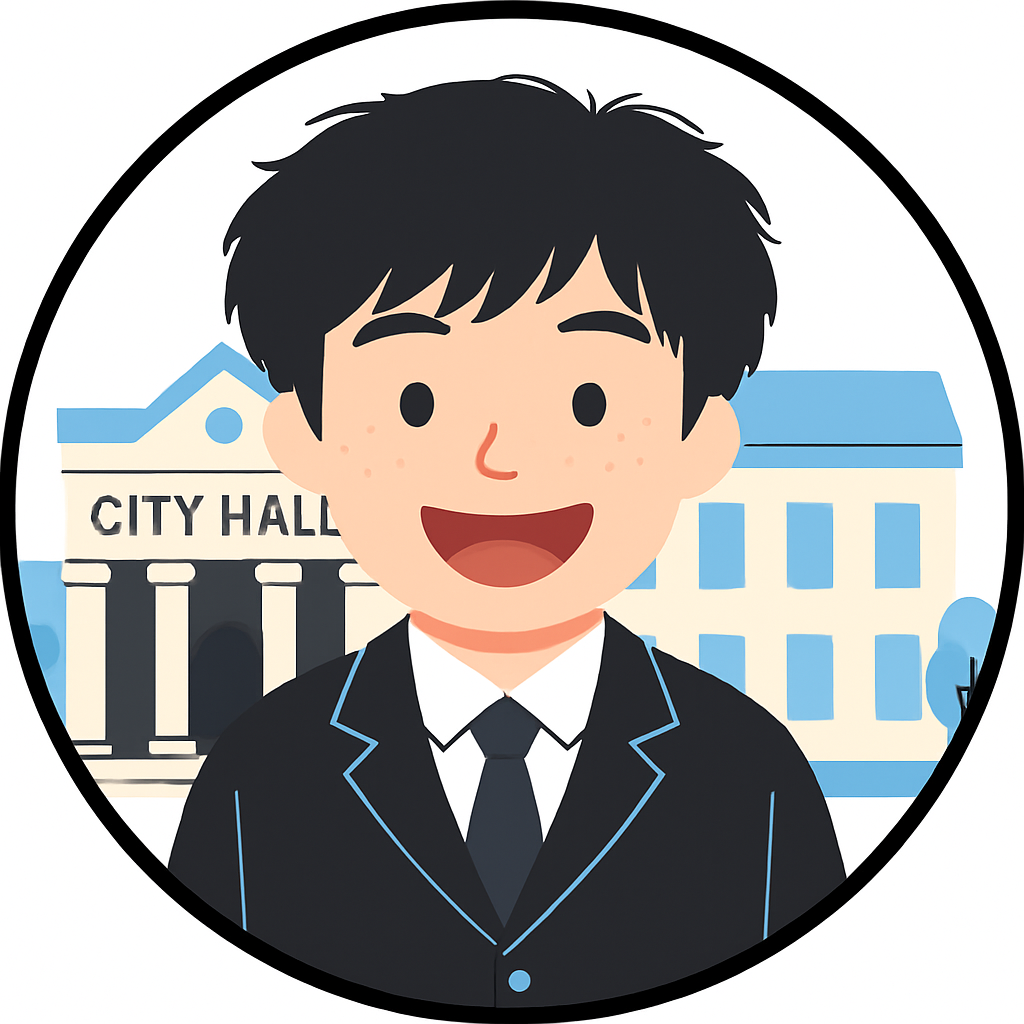
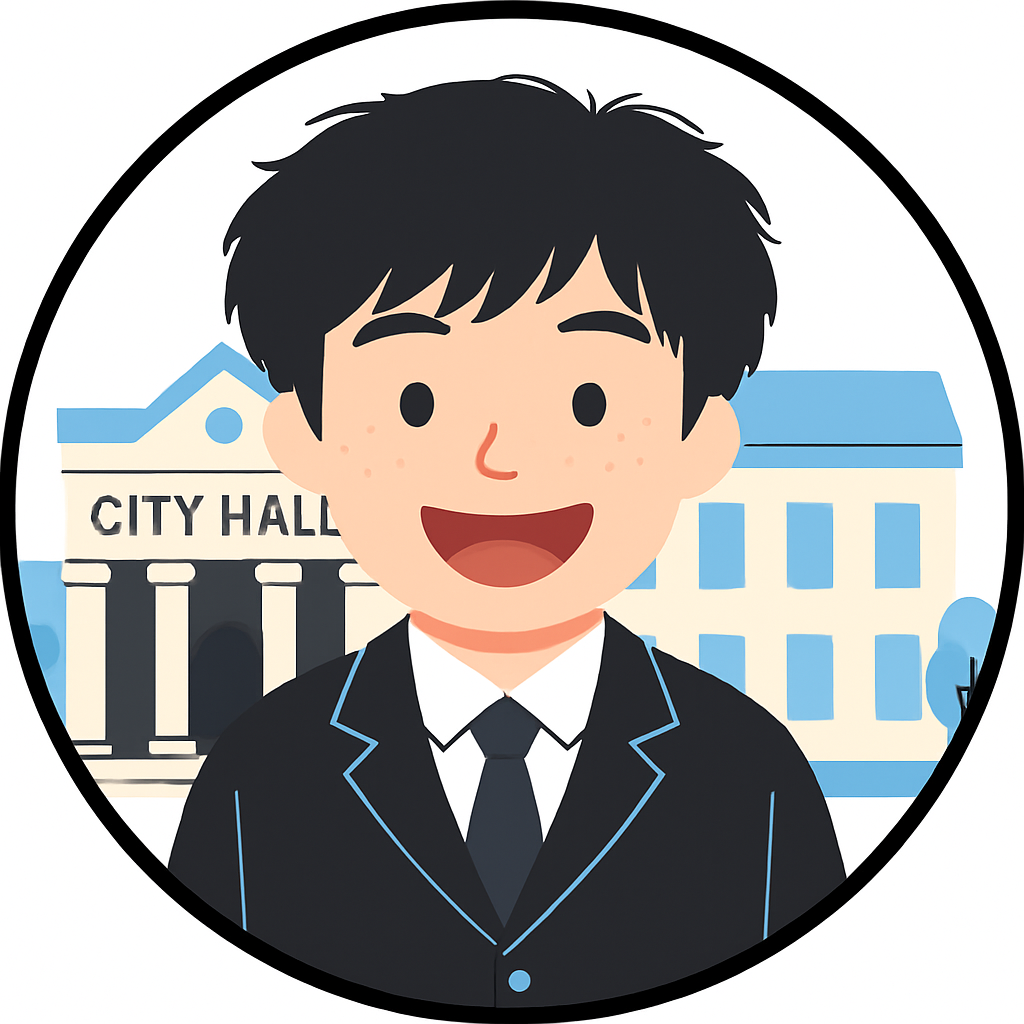
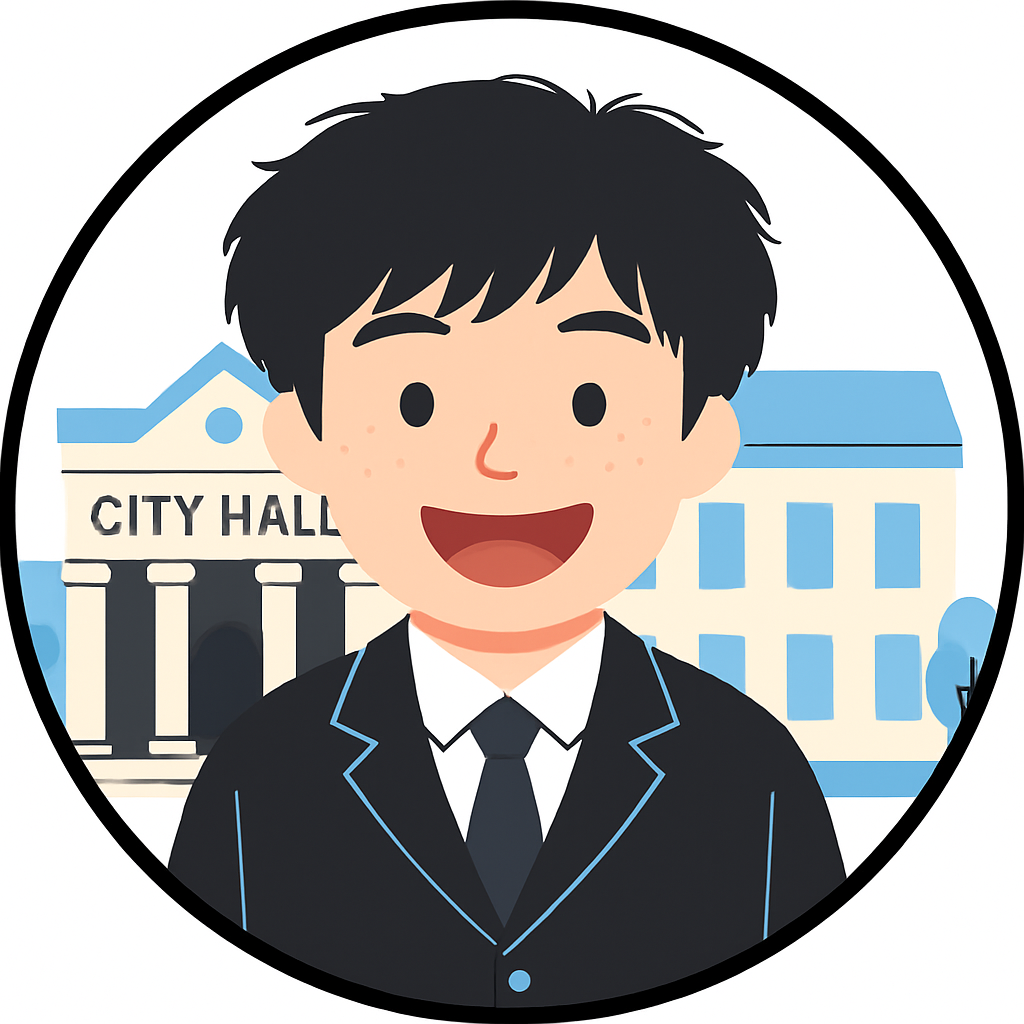
試験対策がわかれば、モチベーションを維持しながら一発合格を目指そう!
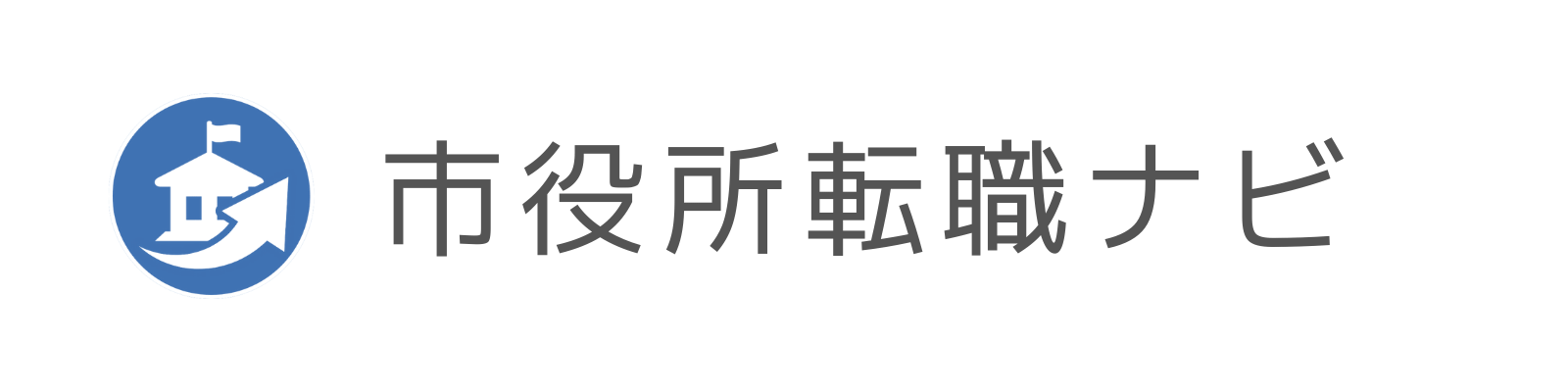


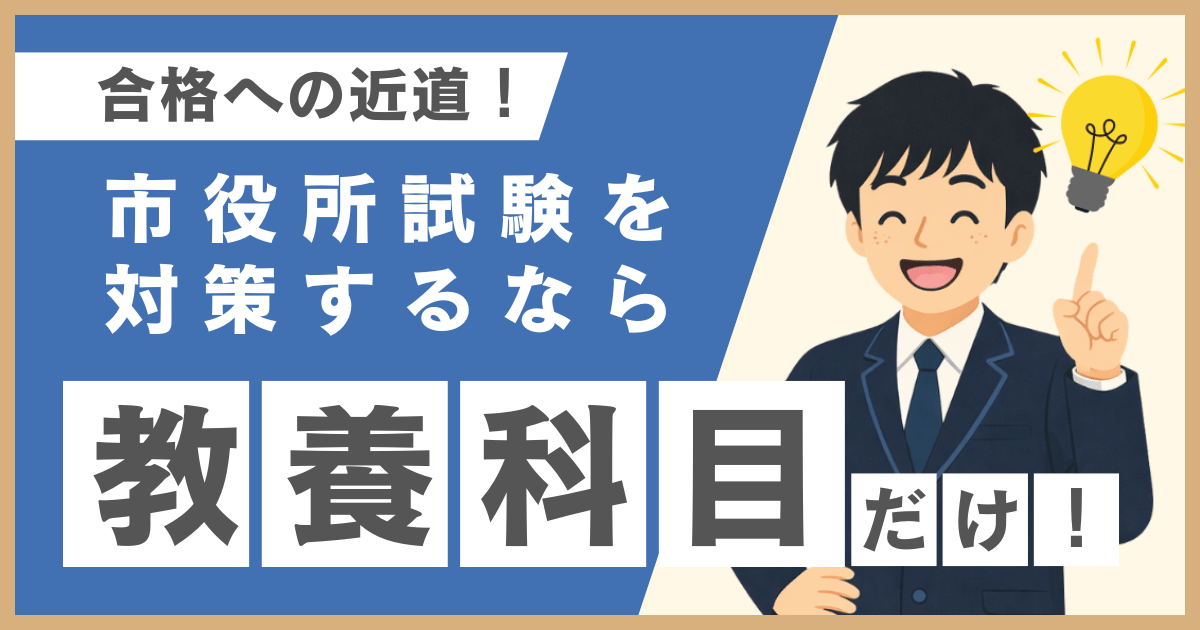
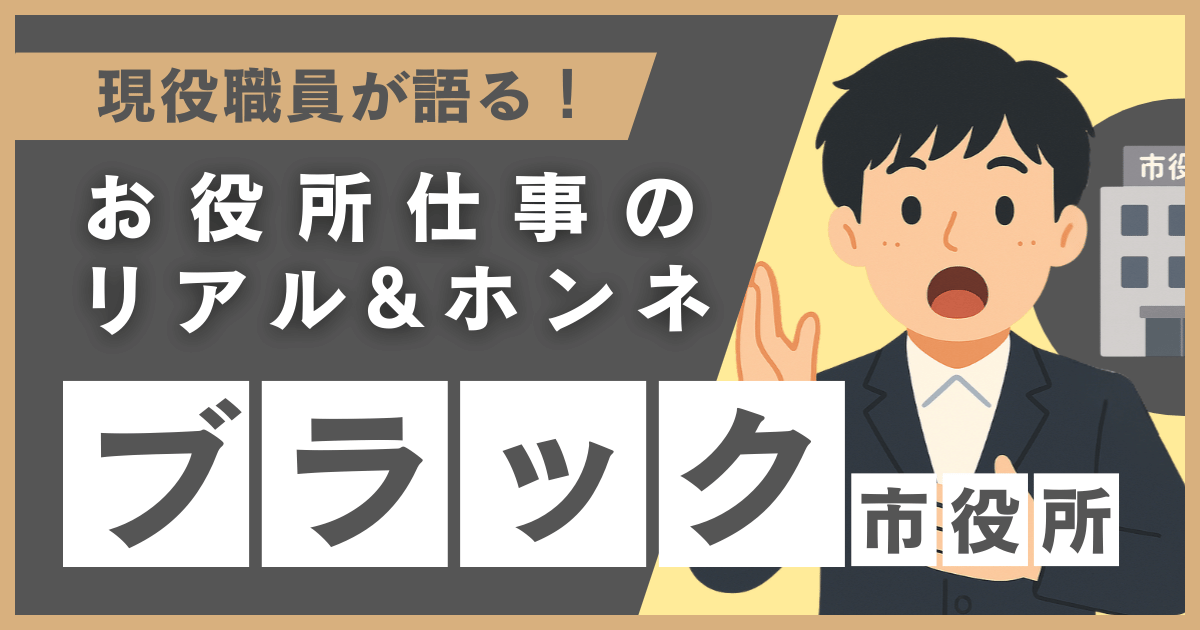
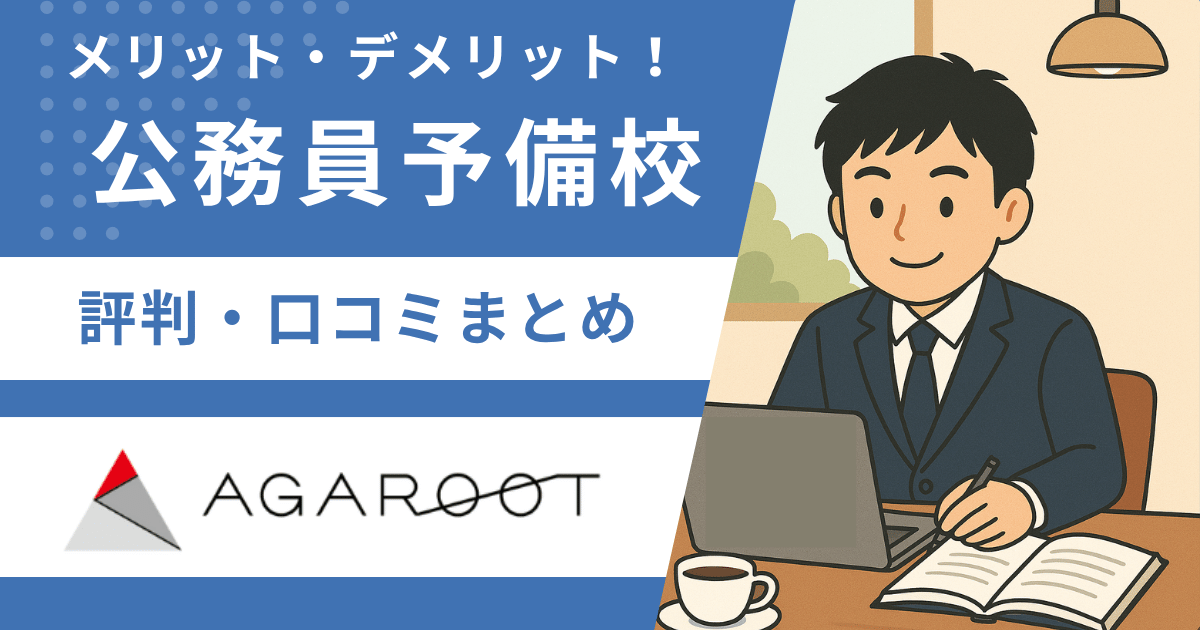


コメント